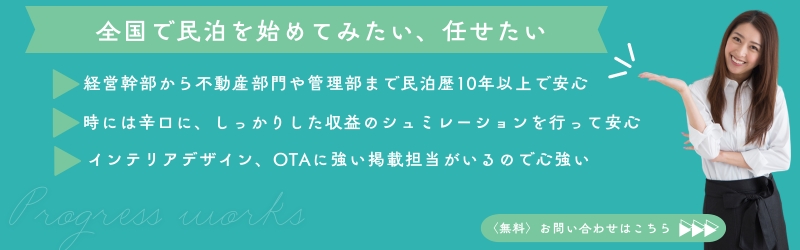特区民泊バブル、終焉へ──生き残るのは“コロナ耐性”のある代行会社だけ
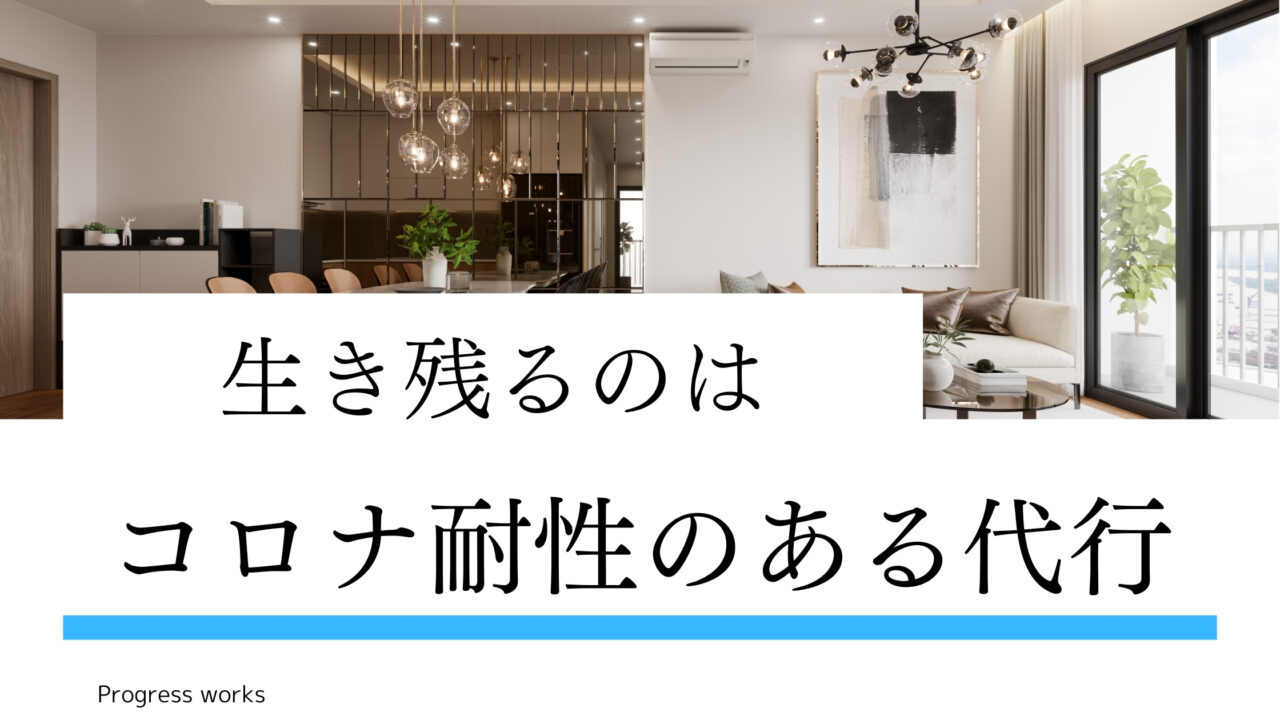
生き残るのは「コロナを乗り越えた民泊運営代行会社」だけかもしれない
今、大阪を中心に再び「制度変化の波」が押し寄せています。
特区民泊──年間365日営業が可能な、宿泊業界における“裏ワザ”とも言えるこの制度が、新規受付停止になる可能性が極めて高まっています。
そしてこの波の中で、運営代行会社の中でも**“生き残るところ”と“消えていくところ”の分岐点**が、静かに、でも確実に現れ始めています。
その分岐点とは、**「コロナ禍をどう乗り越えたか」**です。
民泊運営の“第二の淘汰”が始まる
2020年のコロナ禍では、インバウンド需要が完全に途絶え、観光業は壊滅的打撃を受けました。
民泊業界も同様で、「すべてキャンセルになった」「管理物件をすべて手放した」「半年間収入ゼロ」といった声が全国から聞こえてきた時期です。
あのとき、民泊代行会社は二手に分かれました。
-
一部は撤退し、清掃業や他業種に転換して“民泊”から姿を消した。
-
一部は踏ん張って業態転換・コスト最適化・長期滞在受け入れなどで、なんとか持ちこたえた。
今、特区民泊が終わりを迎えつつあるこの局面で、本当に生き残れるのは、あの激震をすでに経験している会社だけです。
コロナを経験した運営代行会社が強い理由
① 柔軟なオペレーション体制がすでにできている
コロナ禍では、キャンセル対応・ゲストの移動制限・衛生対策強化など、日々変わる状況への“即応力”が求められました。
その経験がある会社は、制度変更や運営規制の変更にもすぐに対応できる体制をすでに持っています。
② 依存しないポートフォリオを作れている
特区民泊“だけ”で食べていく危うさを、コロナ禍で身をもって知った代行会社は、住宅宿泊事業法(180日制限)物件や簡易宿所(旅館業許可)などへの移行ノウハウも蓄積しています。
③ ピンチ時のオーナー対応力に差が出る
「突然の規制で営業ができない」という時、パニックに陥る会社と、冷静にオーナーと話し合い、出口を提示できる会社では信頼度がまるで違います。コロナを通じてそうした危機対応力が鍛えられているのです。
一方、コロナ後に“特区バブル”で始めた会社は…
逆に、コロナ収束後の2022〜2024年頃に特区民泊ブームに乗って立ち上がったばかりの代行会社は、この制度停止の波に非常に弱い構造をしています。
-
特区民泊のみ対応可能(180日制限や旅館業には未対応)
-
新規獲得が営業の生命線
-
イレギュラー事態への対応経験がほぼゼロ
こうした代行会社が、制度の足元が崩れる中で持ちこたえるのは非常に困難です。
代行会社を選ぶなら「実績年数」より「危機経験」
代行会社を選ぶ際、つい「実績年数」や「管理件数」だけを見てしまいがちです。
でも、本当に見てほしいのは、
**「あなたの会社は、コロナ禍をどう乗り越えましたか?」**という一点です。
この問いに対して、具体的なエピソードや数字を出して答えられる会社は、どんな制度変更にも対応する準備ができていると見ていいでしょう。
特区民泊制度の終焉は、“本物の会社”を見極めるタイミング
制度が簡単で、誰でも収益が出せた時代には、運営代行会社も“数だけ”で戦えました。
でも、制度が複雑になり、行政の判断が刻一刻と変わる今のフェーズでは、“本物だけが残る”業界になります。
それはもう、コロナのときに一度、証明されているのです。
まとめ:ピンチを経験した者だけが、次のフェーズへ進める
特区民泊の新規受付停止という制度的変化は、確かに打撃です。
でもそれ以上に、この業界でまた一つ“経験者と未経験者の差”が明確に分かれる局面でもあります。
生き残るのは、ただ施設を掃除してカギを渡す会社ではありません。
ピンチの時に逃げなかった会社、踏みとどまって工夫した会社、そしてその経験を“ノウハウ”として活かせる会社です。
コロナを超えた運営代行会社は、もう一度、変化の波を超えていけるはず。
これから民泊運営を誰に任せるか、オーナーが本当に考えるべきタイミングが、今なのです。