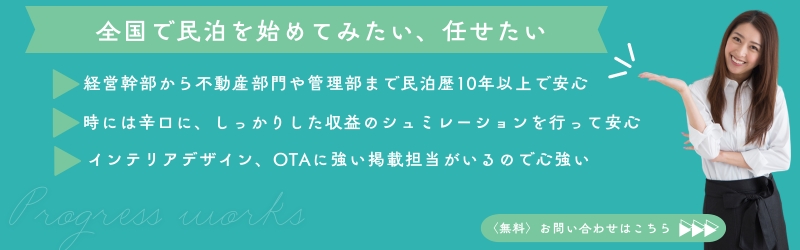特区民泊 新規受付停止説がもたらす波紋──東京発の民泊運営会社、大阪からの静かな撤退

2025年秋、民泊業界に新たな動揺が広がっている。大阪市を中心に実施されてきた「特区民泊制度」において、新規受付の停止が現実味を帯びてきたという未確認の情報が業界関係者の間でささやかれている。この「停止説」が濃厚になるにつれ、東京など遠隔地を拠点とする民泊運営会社が大阪から静かに、しかし着実に撤退を始めている。
コロナ禍で経験済みの「撤退の記憶」
実はこの流れ、まったくの初めてではない。2020年、世界を襲った新型コロナウイルスのパンデミックにより、訪日外国人観光客は激減し、民泊市場は一時壊滅的な打撃を受けた。当時、多くの東京発の民泊運営会社は、大阪に構えていた運営拠点や物件を次々と閉鎖・売却し、地元企業や個人事業者に事業を譲渡するかたちで撤退していった。
その後、観光需要の回復とともに再び大阪に参入する企業も現れたが、2025年に入り、再び「撤退」の動きが加速し始めている。理由は明確だ。「制度の先行きが不透明」であり、「遠隔地ゆえに人員配置が困難になりつつある」からである。
特区民泊制度とは何か
「特区民泊」とは、国家戦略特区を活用した制度で、旅館業法の特例措置として設けられたものだ。大阪市はこの制度を活用し、比較的早い段階から民泊の活性化を図ってきた。通常の住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)では年間180日までの営業制限があるが、特区民泊はこの制限がなく、365日営業が可能なため、運営効率が高く、収益性に優れるというメリットがある。
この制度の恩恵を受け、大阪には数多くの特区民泊物件が誕生し、とりわけインバウンド需要の高まりとともにその価値を高めてきた。しかし、ここに来て、その「新規受付」が止まるかもしれないという話が出てきたのである。
行政の対応と制度の不確実性
現時点で正式な発表はなされていないものの、「新規受付の停止」という情報が広まりつつある背景には、大阪市の内部での制度見直し、あるいは国からの方向転換があると噂されている。観光政策の再編や、地域住民との軋轢、違法民泊の問題など、制度の見直しを促す要因は少なくない。
運営会社にとって最も恐れるのは、「制度の不確実性」だ。特区民泊は地方自治体との協調によって成り立つ制度であり、その方針が突然変更される可能性がある以上、ビジネスリスクは常につきまとう。
遠隔地ゆえの撤退判断──人材配置の限界
東京を本拠地とする民泊運営会社が大阪から撤退するもう一つの理由は、現場の「人員配置」の難しさである。特にトラブル対応や清掃・点検といった現地業務の質を維持するには、ある程度のスタッフ数とマネジメント力が求められる。しかし、制度の将来が不透明な大阪に今後も人材リソースを継続投入する合理性が薄れつつある。
これまで全国展開を掲げていた企業でさえ、採算性の不確実な地域への投資を再考し始めている。将来的に特区民泊の新規供給がストップし、既存物件の入れ替えや拡大ができなくなるとすれば、その地に人を配置する理由は薄れ、やがて撤退という選択肢が現実味を帯びてくるのは自然な流れとも言える。
今後の業界への影響
このような動きが本格化した場合、民泊業界には複数のインパクトが生じるだろう。
-
大阪市場の縮小:新規供給が止まり、撤退が相次げば、物件数は徐々に減少に転じる。
-
価格上昇の可能性:物件数が減れば、宿泊単価が上昇する可能性もある。特にインバウンド需要が強い状況では、限られた物件に予約が集中しやすい。
-
地元企業の再評価:遠隔地企業の撤退により、大阪を地盤とする地場企業にとっては好機となるかもしれない。地元ネットワークを活かした柔軟な対応力が評価される可能性がある。
-
代替制度への移行:特区民泊に代わる別の制度や形態(例えば簡易宿所やホテル形態)へのシフトも予想される。
「撤退」はあくまで戦略的判断──今後を見据えた柔軟な動き
誤解してはならないのは、撤退=失敗ではないということだ。多くの民泊運営会社にとって、地域ごとの制度リスクや運営コストを冷静に見極め、事業ポートフォリオを再編することは当然の戦略である。むしろ不確実性が高まる中で、リスクを最小限に抑えつつ成長機会を探る姿勢は、企業としての成熟を感じさせる。
今後、仮に大阪の特区民泊制度が本当に「新規受付停止」となるならば、その影響は地元だけでなく、全国の民泊戦略にも波及していくだろう。運営者、投資家、宿泊者──誰にとっても、注視すべき「転換点」が今、訪れようとしている。