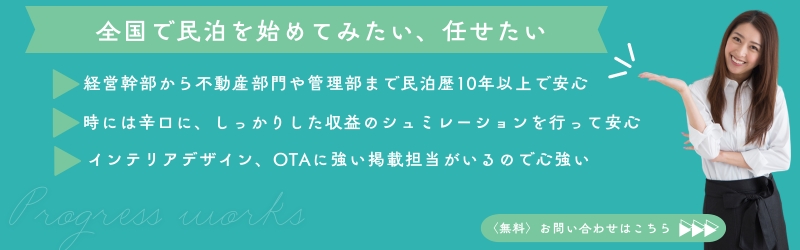「通報」の皮をかぶった犯罪──民泊施設を狙う近隣住民の嫌がらせの実態
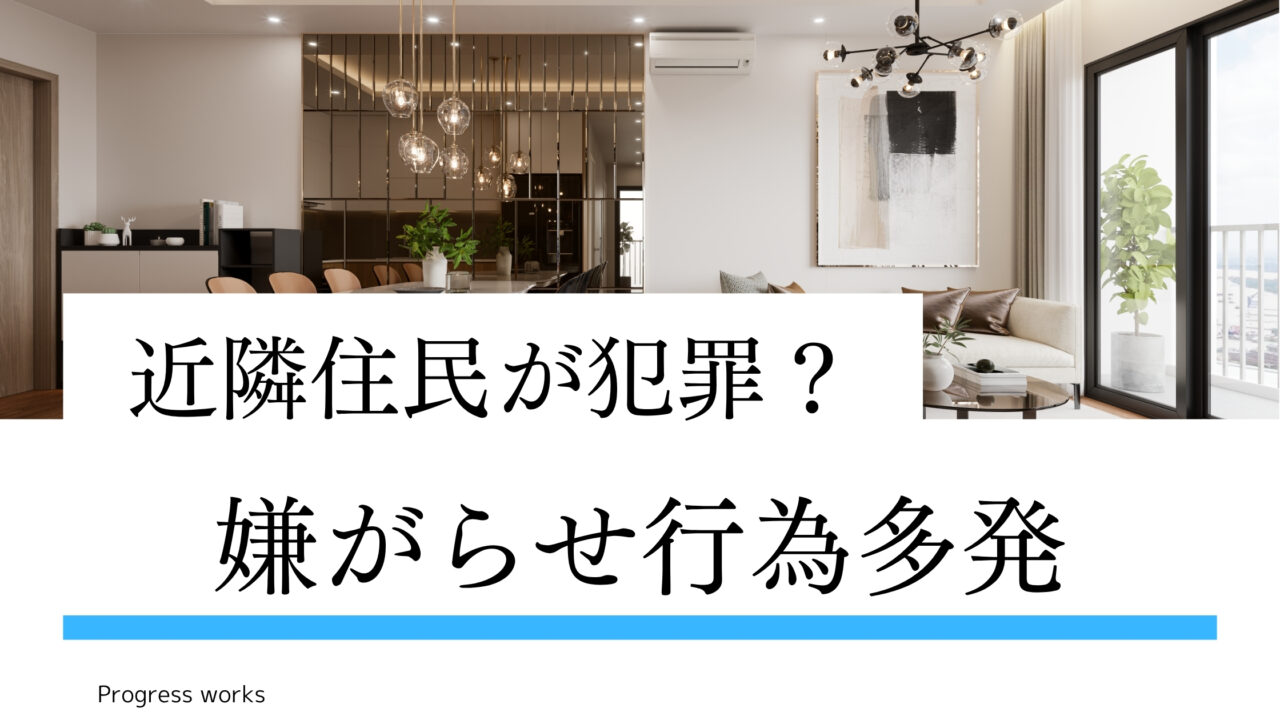
〜民泊施設を狙う嫌がらせ行為と、その法的責任〜
民泊業界では今、行政による規制強化が相次いでいます。
大阪市では特区民泊の新規受付が停止され、各自治体では住宅宿泊事業法への上乗せ条例が加速。さらに、夜間対応や現地駆けつけ対応の義務化など、「個人ホストの排除」とも取れる流れが顕著になってきました。
しかし、こうした法規制の“外側”で、今じわじわと運営者を追い詰めているもう一つの問題があります。
それは──
近隣住民による「民泊施設・ゲストへの嫌がらせ」です。
防犯カメラが当たり前になった今、これまで“言いがかり”で済まされていた行為が、証拠として可視化され始めています。
そして中には、明確に「犯罪」として扱われ得る行為も多いのが現実です。
こんな“あるある”が、実は犯罪行為です
民泊施設を運営していると、次のような出来事を耳にしたり、経験したことがある人も多いでしょう:
-
ゲストが出したわけではないゴミが、あたかもゲストの仕業かのように敷地内に投棄される
-
玄関前に煙草の吸い殻が置かれ「ゲストが吸った」と苦情が入る
-
ゲストに対して「外国人は来るな」「ここはホテルじゃない」などの暴言
-
近隣住民が敷地内に無断で侵入し、撮影や備品のチェックを行う
-
防犯カメラに映るようにわざと迷惑行為をすることで、ゲストを“問題人物”に見せかける
これらの行為は、感情的な反発や近隣トラブルという“日常的なすれ違い”のように見えますが、多くが立派な違法行為・犯罪行為に該当します。
法律で見ると、どうなる?
以下に、実際に該当しうる代表的な法令とその内容を挙げてみます。
◎【民法709条】不法行為による損害賠償
他人に対して故意または過失により損害を与えた場合、加害者には損害賠償責任が生じます。
例えば:
-
根拠のない通報により宿泊キャンセルが発生した
-
設備や備品を意図的に破損された
-
悪評を流されレビューが悪化した
これはすべて、不法行為に基づく賠償請求の対象となり得ます。
◎【刑法130条】住居侵入罪
無断で敷地に立ち入る行為は、**正当な理由がなければ「住居侵入罪」**にあたります。
門扉を超えてゴミを投棄したり、敷地内に立ち入って監視・撮影することも、明確に違法です。
罰則:3年以下の懲役または10万円以下の罰金
◎【刑法231条】侮辱罪
◎【刑法230条】名誉毀損罪
ゲストに対して差別的、人格を否定するような暴言を浴びせた場合、それが社会的評価を下げる発言であれば、侮辱罪または名誉毀損罪に該当する可能性があります。
-
「あんな国の人が来るなんて迷惑」
-
「騒音ばかりでトラブルメーカーだ」
-
「ゴミを散らかしていった。迷惑行為の常習者だ」
たとえ事実でなかったとしても、公共の場や他人に広めれば刑事罰の対象になります。
◎【刑法233条】信用毀損罪・業務妨害罪
意図的に「民泊施設は違法だ」「やばい人が泊まってる」などと風評を流す、あるいは虚偽の通報を繰り返す行為は、信用毀損や業務妨害罪に該当します。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
防犯カメラの映像は「証拠」になります
これまで、こうした嫌がらせ行為は「言った・言わない」で片付けられがちでした。
しかし、今やほとんどの民泊施設に防犯カメラが設置されており、行為の一部始終が記録されます。
-
どの時間に、誰が、どこに立ち入り、何をしたのか
-
どんなゴミが、どこから持ち込まれたか
-
どのような発言が、誰に向かってなされたか
このような映像は、警察への相談や訴訟の際の決定的な証拠となります。
むしろ今後、こうした証拠を**「持っていない運営者は守れない」**時代になるかもしれません。
「通報者が正しい」とは限らない時代へ
民泊に対する通報や苦情があると、どうしても行政や警察は「施設側に落ち度があるのでは」と見がちです。
しかし、近年では「明らかに悪意ある通報者」の存在が問題視され始めています。
過剰な通報、虚偽の主張、地域内での誹謗中傷──それらが施設運営を妨害する目的で行われていたとすれば、それは“正当な苦情”ではなく“違法行為”です。
小規模ホストこそ、毅然とした対処を
特に個人で運営しているホストの中には、
-
「波風立てたくない」
-
「地域との関係を壊したくない」
-
「大事にしたくない」
という理由で、泣き寝入りするケースが少なくありません。
しかしそれは、相手の違法行為を容認することにつながり、ますます状況を悪化させます。
具体的な対応策:法的トラブルから身を守るために
-
敷地内に「防犯カメラ作動中」の掲示
→ 予防効果と証拠能力の明示 -
苦情や通報があった場合の記録保存
→ 時系列、内容、関係者を明確にメモ -
被害を受けた場合は必ず警察に相談
→ 証拠を持って相談すれば、民事・刑事の動きが可能 -
地域の管理会社・弁護士と連携して対応方針を持つ
→ 一人で抱え込まない、法的に正しい判断ができる体制を
結論:民泊を守るには「声を上げる勇気」が必要
その権利を脅かす行為──それがたとえ「住民の声」として表面化していても、
それが事実無根の通報であったり、差別的な発言や敷地内への不法侵入を伴うものであれば、それは“正義”ではなく“違法”です。
声が大きいほうが正しいわけではありません。
地域の平穏や治安を守るという大義名分のもとに、民泊という合法的な事業を“排除の対象”とする風潮が広がっているのだとすれば、
それはもはや共存ではなく、差別と偏見による排除の構造です。
民泊運営者には、トラブルを起こさないための努力が求められます。
一方で、不当な攻撃に対しては、泣き寝入りではなく「毅然と法的に対処する姿勢」もまた必要です。
いま、問われているのは「地域との共生」だけではない
これからの民泊運営者は、単に「静かにしていればいい」「ルールを守っていれば問題ない」という時代ではなくなりました。
防犯カメラの設置、記録の保存、法的知識のアップデート、弁護士や管理会社との連携──
“自衛”を前提とした運営体制を持たなければ、民泊業を続けることすら危うくなる時代が、すでに始まっています。
民泊は、観光業の裾野を広げ、空き家問題の解決策となり、地域経済に新たな風を吹き込む存在でもあります。
それを支える運営者が、偏見や悪意のもとに排除されることのない社会へ──
その第一歩は、「それは違法です」と、
声を上げることから始まります。