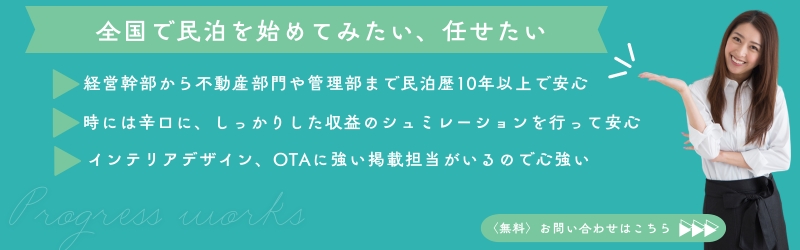これから民泊をやめる人へ|閉業の流れ・必要書類・トラブル回避のポイントを専門解説

はじめに:民泊を「やめる」オーナーが増えている現実
ここ数年、民泊業界では「もう続けられない」「撤退を考えている」というオーナーの声が増えている。
背景には、特区民泊の新規受付停止や住宅宿泊事業法(民泊新法)の上乗せ条例など、制度環境の急激な変化がある。
さらに、罰則の強化、夜間対応の義務化、苦情対応窓口の設置など、運営に必要な負担が増大。
「趣味と副業の延長」で始めた個人オーナーにとっては、もはや片手間で続けられる事業ではなくなっている。
だが実際、「民泊をやめる」と決めても、行政・契約・設備などの面で多くの手続きが発生する。
この記事では、民泊閉業の流れ・必要書類・注意点を専門的にわかりやすく解説する。
民泊を閉業するときの基本的な流れ
民泊の閉業手続きは、どの制度で運営していたかによって異なる。
まずは、自身の物件が「住宅宿泊事業法」「特区民泊」「旅館業法(簡易宿所等)」のどれに該当するかを確認しよう。
● (1)住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の場合
住宅宿泊事業法で登録している場合、営業をやめる際には**「住宅宿泊事業廃止届出書」**を自治体へ提出する必要がある。
提出先は、登録を行った自治体の観光課・保健所など。
必要書類の例:
-
住宅宿泊事業廃止届出書
-
登録番号、住所、廃止日を記載した書面
-
身分証明書(個人)または登記事項証明書(法人)
提出後、自治体の確認を経て正式に「廃止」となり、登録番号が無効化される。
廃止届を出さずに放置すると、定期報告(年6回)の未提出扱いとなり、行政指導や過料の対象になる恐れがある。
● (2)特区民泊(国家戦略特区制度)の場合
特区民泊で運営している場合は、**「特定認定の取消届(廃止届)」**を自治体に提出する。
これは運営を停止する日から概ね10日以内が目安とされており、
書式や提出先(旅館業課・住宅政策課など)は自治体ごとに異なる。
重要なのは、特区民泊には住宅宿泊事業法のような「定期報告義務」は存在しないという点だ。
しかし、宿泊者名簿の保管義務(3年間)や外国人宿泊者の本人確認・記録の保存などは引き続き求められるため、廃止後もしばらくデータを保管しておくことが望ましい。
また、自治体によっては、廃止後も「廃止理由」や「建物用途変更」に関する書面の提出を求められる場合があるため、事前に担当課に確認しておくと安心だ。
● (3)旅館業許可(簡易宿所など)の場合
旅館業法に基づいて営業許可を受けていた場合は、**保健所に「営業廃止届」**を提出する必要がある。
許可証の返納を求められる場合も多く、消防署や建築指導課への報告が必要なケースもある。
特に簡易宿所型の民泊は、用途変更・消防設備・建築基準などが絡むため、関係部署へ同時に確認するのが確実だ。
閉業時に発生する契約・費用トラブル
行政手続き以外にも、民泊をやめる際には賃貸契約・設備・委託契約の整理が欠かせない。
特に賃貸物件で運営していた場合は、次の点に注意が必要だ。
● 賃貸借契約の解約と原状回復
民泊目的で借りていた物件は、通常の住居契約と異なり、3〜6か月前の解約予告期間が定められていることが多い。
突然の撤退を決めても、その期間分の家賃支払い義務が残る場合がある。
また、原状回復費用(壁紙・床・家具撤去・残置物処理など)は数十万円規模になることもあるため、
オーナーへの書面通知と見積もり確認を早めに行うことが大切だ。
● 清掃・管理代行会社との契約解除
管理代行業者との契約も、最低契約期間や解約金が定められている場合が多い。
一方的に「今月で終了」と伝えるとトラブルになりやすいため、**契約書の「解除条項」**を必ず確認してから解約手続きを行おう。
● 家具・家電・リネンの処分
民泊用に揃えた備品は、リユースや寄付、買取業者の利用がおすすめ。
放置して退去すると、廃棄物処理違反や追加請求の対象になることもあるため注意。
廃止届を出さずに放置するリスク
「もう営業していないから放っておこう」というケースが意外と多い。
しかし、住宅宿泊事業法では廃止届を出さない限り登録が有効のままとなる。
営業実態がなくても、報告義務を果たしていない登録者として行政に記録が残る。
また、特区民泊の場合も、認定を受けたまま放置していると、自治体の現地調査や更新確認で「運営実態なし」とされ、
将来的な再申請時に不利に扱われる可能性がある。
「やめた後の書類提出」こそ、民泊オーナーにとって最後の責任といえる。
閉業後の税務・保険の整理も忘れずに
個人事業として民泊を行っていた場合は、税務署に**「個人事業の廃業届出書」を提出する。
青色申告者は「青色申告取りやめ届出書」**も必要。
これを出さないと翌年以降も開業扱いのままとなり、不要な書類が届くことがある。
また、火災保険・民泊保険・損害賠償保険など、民泊専用プランを契約していた場合は、解約や内容変更を行う。
自動更新で保険料が引き落とされるケースもあるため、閉業時に必ず確認しておこう。
閉業トラブルを防ぐ3つのポイント
-
早めにスケジュールを立てる
→ 契約解除・行政手続き・撤去作業の時期を逆算して準備。 -
専門家と相談する
→ 行政書士や管理会社、不動産オーナーに事前相談し、手続き漏れを防ぐ。 -
書面・記録を必ず残す
→ 解約通知・届出控え・メール履歴などは、万が一のトラブルに備えて保存。
まとめ:民泊の“やめ方”も経営判断のひとつ
民泊は「始める」よりも「やめる」方が難しい。
だが、制度の変化が激しい今、撤退もまた立派な経営判断だ。
重要なのは、「正しいやめ方」を知り、トラブルやリスクを最小限にすること。
特区民泊でも住宅宿泊事業法でも、最後まで法令を遵守して締めくくることが、次のチャンスへの第一歩になる。