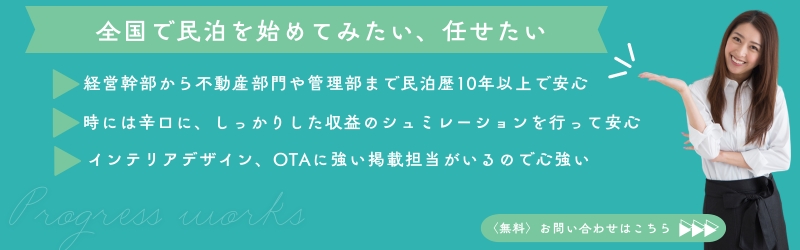行政監査が入ったらどうする?民泊オーナーが知っておくべき実務対応とリスク管理

はじめに:監査は“突然やってくる”
近年、全国で**民泊に対する行政監査(立入検査・実地調査)が増加している。
住宅宿泊事業法や旅館業法、特区民泊条例などの運用が定着するにつれ、
各自治体は「無届営業の取り締まり」だけでなく、“登録済み施設の適正運営”**にも重点を置くようになった。
実際、京都市・大阪市・那覇市など主要都市では、2024年以降に抜き打ち調査・書類確認の件数が増加。
事前連絡なしで監査担当者が現地を訪れるケースもある。
「うちは問題ないはず」と油断していると、記録不備や管理者不在を指摘されることも。
この記事では、民泊オーナーが知っておくべき行政監査の流れと実務対応、リスク回避のポイントを専門的に解説する。
行政監査とは何か?その目的と根拠
● 法的根拠
行政監査(立入検査)は、
-
住宅宿泊事業法第13条・第14条
-
旅館業法第5条
-
特区民泊条例(各自治体)
に基づき、自治体職員が営業の実態確認・法令遵守状況の調査を行う制度である。
監査の目的は「違反を見つけて罰すること」ではなく、
適正な運営を指導・改善させることにある。
ただし、重大な違反が見つかれば営業停止・登録取消・罰金の対象にもなりうる。
行政監査の主なパターン
行政によるチェックは、以下の3パターンで行われることが多い。
| 区分 | 内容 | 対応の特徴 |
|---|---|---|
| 書面監査 | 年次報告や帳簿・宿泊者名簿の提出確認 | 事前通知あり/郵送やメール対応可 |
| 実地監査 | 現地訪問による設備・掲示物・名簿確認 | 抜き打ち・現場立入あり |
| 苦情対応型調査 | 近隣住民・消防・警察などからの通報を受けた調査 | 突然の訪問・現場確認が多い |
特に「実地監査」「苦情対応型調査」は、事前に日程調整がないことが多く、
現場スタッフや管理代行会社の対応品質が問われる。
監査でチェックされる主な項目
行政監査では、以下のポイントを重点的に確認される。
自治体ごとに多少異なるが、共通するチェック項目は次の通り。
【書類関連】
-
届出証・認定証・旅館業許可証などの原本の提示
-
宿泊者名簿の記録内容(氏名・住所・国籍・宿泊日数)
-
外国人宿泊者の本人確認書類(パスポート写し等)
-
管理者情報(24時間対応体制・苦情窓口)
-
清掃・消毒記録、ゴミ分別掲示の有無
【現地確認】
-
玄関・部屋の掲示物(届出番号・管理者情報など)
-
消火器・火災報知器・避難経路図の設置状況
-
ゴミ置き場・騒音対策の実施状況
-
鍵の保管方法・セキュリティ管理
-
無人運営の場合の連絡体制・入退室管理方法
【行政が重視する3要素】
-
宿泊者の安全確保(消防・防災)
-
地域生活への影響防止(騒音・ゴミ問題)
-
本人確認・記録保存(不法滞在防止)
監査が来たときの正しい対応手順
(1)まずは落ち着いて身分証を確認
担当者は自治体職員または保健所・観光課の職員。
必ず職員証・身分証を提示してもらい、訪問目的を確認。
身分が確認できない場合は、電話で自治体の代表窓口へ照会しても問題ない。
(2)書類・掲示物をすぐに提示できるようにする
最も多い指摘が「届出証が掲示されていない」「宿泊者名簿をすぐに出せない」というケース。
現地に紙ファイルを常備し、以下をすぐ取り出せる状態にしておくこと。
-
届出証・認定証・許可証のコピー
-
宿泊者名簿(紙・デジタルいずれでも可)
-
管理者・緊急連絡先一覧
-
消防設備点検報告書(あれば)
(3)質問には正直に、わかる範囲で回答する
虚偽の説明はNG。
不明点は「担当者に確認します」「後日資料を提出します」と正直に伝える。
曖昧な返答よりも、正確な報告を重視する姿勢を示す方が印象が良い。
(4)指摘事項は記録し、改善報告を行う
監査後に「改善指導書」や「口頭指導」を受ける場合がある。
その際は、対応内容を記録し、写真付きで改善報告を提出する。
提出期限を過ぎると「未対応扱い」になるため注意。
よくある指摘・違反事例とリスク
| 指摘内容 | 想定される行政対応 | 対策ポイント |
|---|---|---|
| 管理者の夜間不在 | 指導・再教育命令 | 夜間電話対応・代行委託契約を明記 |
| 宿泊者名簿の未記録・保存不備 | 文書指導/過料(住宅宿泊事業法第15条) | 3年間保存・定期バックアップ |
| 消防設備の未設置・点検漏れ | 立入停止・改善命令 | 消防設備士の点検を年1回実施 |
| 外国人本人確認の未対応 | 指導・改善要請 | パスポート写しを電子保存/本人署名欄確保 |
| 無届で用途変更が必要な改装 | 行政指導・使用停止命令 | 建築士・行政書士に事前確認を依頼 |
特に「管理者体制」と「記録保存」は全国的に重点監査項目。
代行会社に委託している場合でも、最終責任は届出者(オーナー)本人にある。
監査に備えて日常的にすべき3つの準備
-
書類フォルダを現地常備
→ 届出証・名簿・連絡表を一式まとめて保管。 -
清掃会社・代行業者と情報共有
→ 現場スタッフが監査時に対応できるよう、連絡フローを共有。 -
年1回の内部点検を実施
→ 消防・設備・掲示・名簿管理を自主チェック。
定期的に自分で「簡易監査」を行うことで、行政からの指摘を防げる。
指導・処分を受けた場合の対応
もし「改善命令」や「営業停止命令」を受けた場合でも、
多くは誠実な改善報告で再開可能である。
-
改善内容を写真付きで報告
-
対応した日時と担当者名を明記
-
再発防止策を添付
「逃げずに対応する」ことが最善のリスク管理。
逆に無視や虚偽報告をすると、登録取消や罰金のリスクが高まる。
監査をチャンスに変える考え方
行政監査はネガティブな出来事ではない。
むしろ、運営体制を見直す絶好の機会である。
-
掲示物やマニュアルを更新
-
管理代行会社の体制を再点検
-
消防・建築の再チェック
こうした改善を経ることで、レビュー評価や再稼働率の向上にもつながる。
監査対応の質は、事業者としての信頼度そのものと言える。
まとめ:監査は“恐れるもの”ではなく“整えるきっかけ”
行政監査は、真面目に運営している民泊オーナーにとって
「不安」よりも「チャンス」にすべきイベントである。
重要なのは、
-
書類と現場を常に整えておくこと
-
代行会社やスタッフと連携を取ること
-
改善要請には誠実に対応すること
監査対応をきちんと行うオーナーは、行政からの信頼が厚くなり、
結果的に長期的な運営安定とブランド力向上につながる。