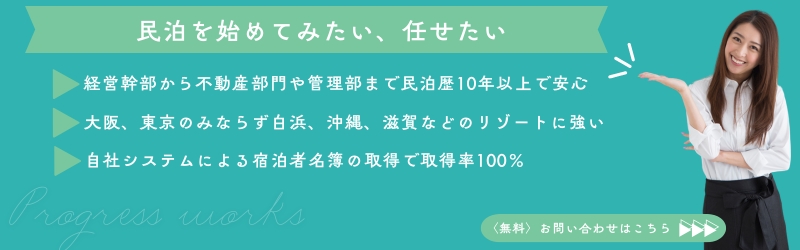「電話がつながらない民泊」問題——夜間の苦情対応不在が地域に与える深刻な影響

~“管理体制が整っていない民泊”は地域の信頼を失う~
大阪では、インバウンド需要の回復により民泊の再拡大が進んでいるが、その一方で地域住民からの「夜間トラブル」の苦情が急増している。
特に目立つのが、**騒音や迷惑行為に関する苦情を伝えるために電話をかけても「つながらない」「外国人が出て日本語が通じない」「折り返しがない」**といった、苦情受付窓口そのものが機能していないというケースだ。
■ 民泊制度には「連絡先設置」の義務がある
住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)や旅館業法では、次のような管理義務が定められている:
「宿泊者や近隣住民からの苦情その他の問い合わせに、適切かつ迅速に対応するための体制を整備すること」(住宅宿泊事業法 第9条)
つまり、民泊を運営する者は、24時間連絡可能な苦情受付窓口を設けることが義務づけられている。これは単なる形式ではなく、地域社会との信頼関係の土台を成す非常に重要な要件である。
■ 実際に起きている問題
📍電話が「無言の留守番電話」に接続される
→ 近隣住民が深夜の騒音トラブルを通報しようとしたが、窓口電話に出ず、翌日になっても折り返しがなかった。
📍対応者が外国人で日本語が通じない
→ 苦情を伝えても「ワカリマセン」「English only」と言われ、事実上の放置。
📍番号が古くて使用されていない
→ 届出に記載されている番号が、すでに使われていないか、別のコールセンターに転送されている。
📍電話には出るが「何もできない」
→ 苦情対応をアルバイトに任せているケースも多く、実質的な解決策を提示できず、「上に伝えます」で終わる。
■ 地域住民の怒りと「民泊不信」
このような対応不備は、すぐに**「民泊は迷惑」「近所から追い出してほしい」**という声に直結する。特に高齢者が多い地域や、子育て世帯の多い住宅街では、騒音や深夜の出入りが命に関わるストレスとなることもある。
そして一度信頼を失えば、以下のような連鎖が始まる:
-
地域住民が自治体へ通報 → 行政指導
-
管理組合が民泊営業停止を求めて動く
-
ネガティブな口コミが蓄積 → 稼働率低下
-
管理不備が再発 → 届出取消・営業停止処分
■ トラブルの多くは「形だけの管理体制」から生まれている
届出や書面上では「苦情受付24時間体制」と謳っていても、実際は以下のような実態が多い:
-
苦情窓口は、海外在住のオーナーが個人携帯で兼務
-
対応スタッフが常駐しておらず、外注も教育されていない
-
苦情件数の記録・報告体制がなく、内部でも把握されていない
これは、**地域との共存を軽視した「収益優先の運営」**の現れであり、持続可能なビジネスとは程遠い。
■ 実務的な改善策:信頼される民泊のために
✅ 民泊運営会社に委託する
民泊運営会社を活用する。対応は多言語可能・即時対応・報告記録の対応など充実。
✅ 苦情記録・再発防止策の運用
すべての苦情を記録し、月ごとに集計・分析・改善策を検討することで、再発を防ぎ、自治体や住民にも誠意を示せる。
✅ 看板・掲示で連絡先を明確化
物件の出入口や共用部に、苦情連絡先(電話番号・対応時間・言語)を多言語で掲示し、信頼性を可視化する。
■ まとめ:「電話1本に応えられるか」が民泊の信用を決める
民泊は、地域の理解と協力がなければ続けられないビジネスである。そしてその信頼関係は、夜中の1本の電話にきちんと応えられるかどうかにかかっている。
「電話に出ない」「外国語しか通じない」「対応できない」——これは単なるミスではなく、地域との信頼関係を裏切る重大な問題だ。
観光都市・大阪で民泊を持続可能なビジネスにするために、運営者は「対応力=経営力」と認識し、苦情窓口の品質向上を最優先課題として取り組むべき時が来ている。