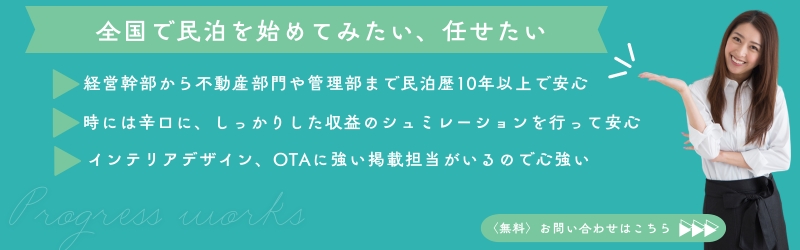特区民泊の申請が急増中──保健所がパンクし、許可取得に“想定外”の時間がかかる現実
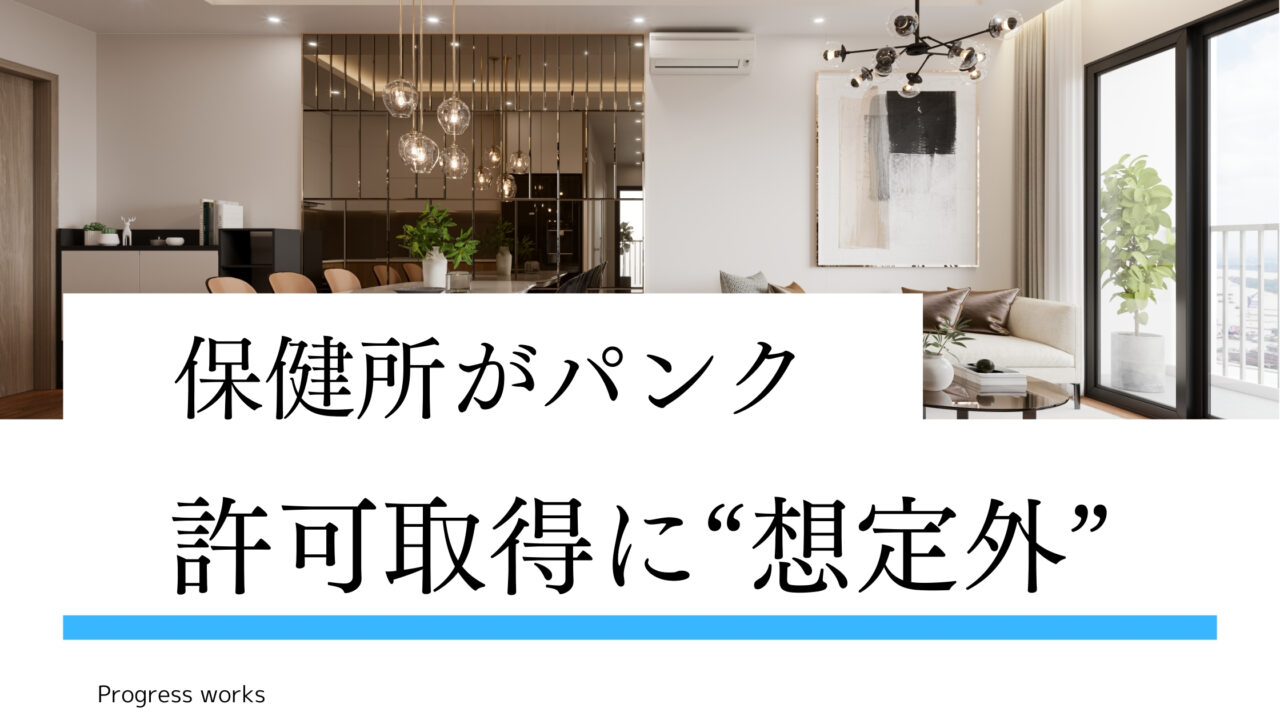
ここ最近、民泊の現場でよく耳にするようになった言葉があります。
「書類は出したけど、いつ許可が下りるかわからない」
「保健所が全然動いてくれない」
「想定より1〜2か月遅れてオープンがずれた」
いま、特区民泊の許可申請が各地の保健所で“パンク状態”になり、開業準備に大きな影響を与えています。
制度上は自由度の高い特区民泊ですが、実務的には「いざ申請しても、審査に何週間もかかる」「何度も修正依頼が返ってくる」という問題が、事業者・オーナーを悩ませています。今回はその実情と背景、そして今後必要な制度対応について、現場目線で整理してみます。
申請数が急増。保健所の処理能力を大幅に上回っている
大阪市や東京都の一部地域など、国家戦略特区での民泊運営を希望する事業者が急増しています。
背景には:
-
インバウンド回復と観光需要の高まり
-
空き家・空室の再活用ニーズの高まり
-
民泊新法(年間180日制限)では採算が合わない物件の逃げ道として、特区民泊を選ぶケースの増加
-
法人だけでなく副業的に始めたい個人オーナーの増加
などがあり、申請件数が一気に膨れ上がっているのです。
特に2025年に入り、大阪市などでは「過去最大級の申請数に達した」とされ、申請受理から実際の許可取得まで、以前なら2〜3週間だったところが、1〜2か月以上かかるケースもざらになってきました。
保健所側の実情:制度はあっても、人手が足りない
民泊の許可申請は、実は非常に手間のかかる作業です。
建築・消防・騒音・設備・近隣説明など多岐にわたる確認項目があり、1件ずつ丁寧に書類確認と現地調査が必要です。
しかし、保健所の人員体制は限られており、現場はこう語ります:
「年間数百件も申請が来ているが、それを処理する担当者はほんの数人」
「コロナ対策も兼任していたスタッフが戻っておらず、業務量に追いついていない」
「1つの申請でも不備があるとやり直しになるため、1件に数時間かかることも」
つまり、制度として“自由に申請できる”仕組みが整っている一方で、審査する行政側のリソースが追いついていないのが現実なのです。
結果、こんな事態が起きている
-
「〇月にオープン予定だったのに、まだ許可が下りない」
-
「予約サイトに掲載したが、キャンセルになった」
-
「内装・設備工事が終わっても、営業が始められないので空室期間が伸びた」
-
「初めての民泊運営で、スケジュールも資金繰りも狂った」
特に、初めて民泊事業を始める個人オーナーや小規模事業者にとって、許可遅延は事業リスクとして致命的になりかねません。
なぜ改善されないのか?制度設計上の“ねじれ”
実は、制度としては「誰でも特区民泊を申請できる」という開かれた仕組みがある一方で、それを支える体制はほとんど強化されていません。
-
新たな申請増を前提とした人員配置・予算配分がされていない
-
DX化(オンライン申請・電子審査)の整備も自治体ごとにバラバラ
-
一度でも書類不備があると、再提出 → 再チェック → 再訪問と、何重にも遅延要因が発生
つまり、“入口は広くしたのに出口は変わっていない”ため、どんどん詰まっていく構造になってしまっているのです。
少しでも早く許可取得をするには?
行政書士は、
-
提出書類の内容を自治体ごとに最適化
-
事前相談や窓口対応の経験が豊富
-
審査官が気にする“細かいポイント”を熟知
しており、書類が一度で通りやすい=許可取得がスムーズになる可能性が高まります。
現場でも「自分で出したら2回差し戻されたけど、行政書士に頼んだら1発で通った」という声は少なくありません。
今後、申請がさらに混み合うことを見越すなら、慣れた専門家と組むことが“時間の投資”として非常に有効です。
📌 現場からの教訓
✅ 特区民泊の申請は「出せばすぐ通る」と思わない
✅ 少なくとも開業予定の2〜3か月前には申請を完了させる
✅ 専門家や運営会社と連携して、書類の正確性を担保する
民泊という仕組みは、都市の空き家問題、観光政策、地域経済など多くの課題に貢献するポテンシャルを持っています。その価値を損なわないためにも、申請者・行政双方が「よりスムーズに、より安全に」進められる制度設計が求められています。
そして今の現場は、その“過渡期”の真っ只中。
事業者としては、焦らず、正確に、戦略的に。民泊の未来を共につくっていく意識が、これからますます大事になるでしょう。