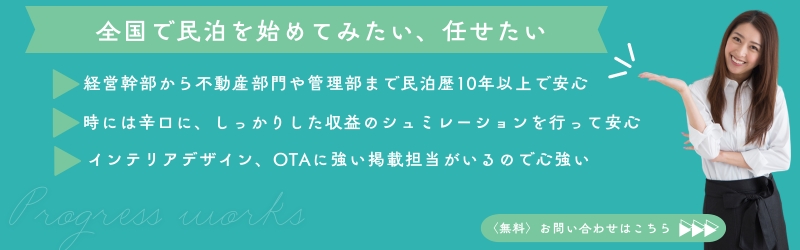民泊運営代行、選別の時代へ:利益が見込めない物件は“お断り”の現実
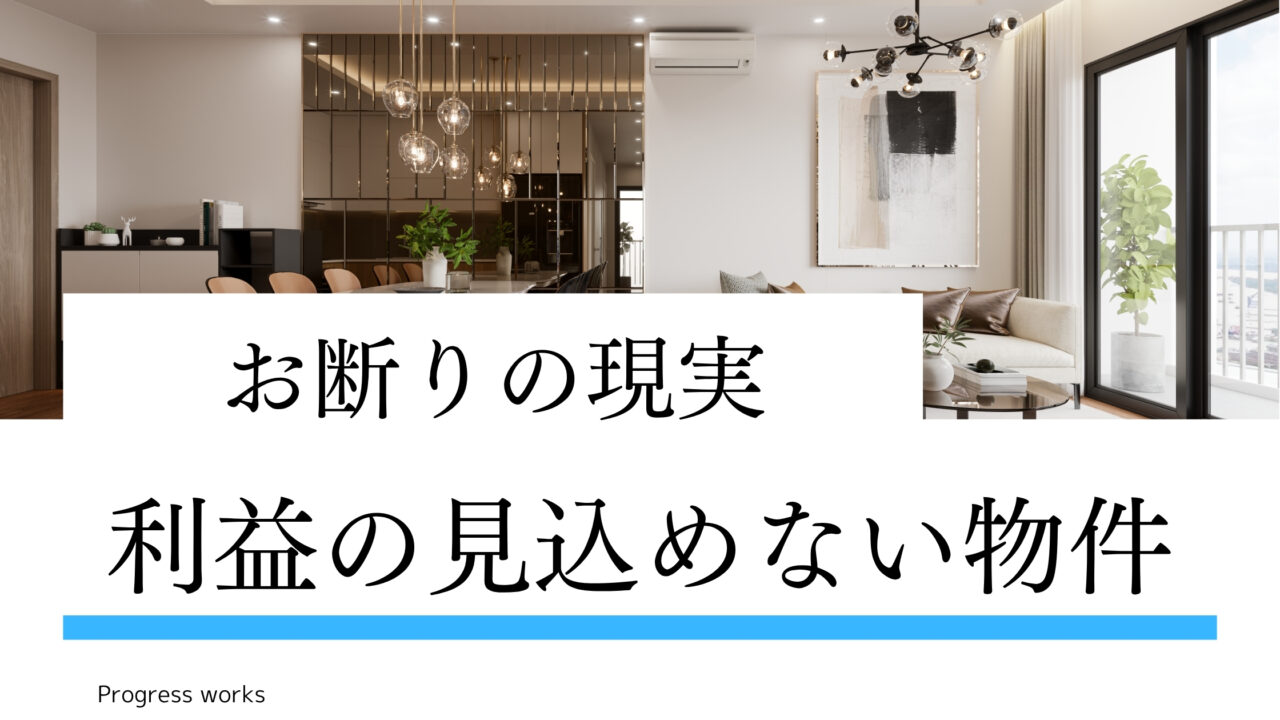
かつてはどんな物件でも、立地や広さを問わず「収益化できる」と期待されていた民泊市場。しかし、2024年以降、その様相は一変しつつある。特に注目されているのが、民泊・貸別荘の運営代行会社が、採算の合わない物件の受託を控えるようになっている現象だ。
民泊業界の“審査時代”とも言えるこのトレンドの背景には、いくつかの大きな要因が存在している。
民泊・貸別荘市場の成熟と“クオリティ競争”
2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行後、爆発的に増加した民泊物件は、全国で一時2万件を超えた。しかし2023年以降、特に都市部・観光地では、競争が激化。
これに伴い、宿泊者はより清潔で、快適で、独自性のある物件を選ぶようになり、レビューの質と運営体制の差が、予約率に直結するようになってきた。
つまり、安価な設備や画一的なインテリアでは、競合に勝てない時代が来たということである。
運営代行会社の“選別眼”の進化
代行会社にとって、物件の運営は単なる管理業務ではない。物件ごとに価格調整、集客施策、清掃手配、カスタマーサポートを行うため、時間もリソースもかかる。
そのため、最近では以下のような条件を満たさない物件は「採算が合わない」と判断され、断られることがある:
-
月売上30万円以下が見込まれる物件
-
駅から遠くアクセスが悪い
-
客室が狭く、定員が2名以下
-
独自性や内装の魅力が弱い
-
地域ルールや管理規約が厳しく、運営リスクが高い
特にリモート対応の自動化が進んだことで、「手のかかる物件を排除し、収益性の高い物件に特化する」動きが顕著になってきている。
貸別荘でも“高級志向”に対応できない物件は不利に
近年は、ファミリー層やインバウンド向けに**「一棟貸し」型の貸別荘**の人気が高まっている。
だがこの分野でも、
-
温泉付き
-
キッチン・調理器具完備
-
プライベート空間を重視した設計
-
ペットOK、サウナ付きなどの付加価値
といった“ハイエンド化”が進んでおり、旧来の簡素な別荘では競争に埋もれてしまうリスクがある。代行会社もこれを見越し、高単価・長期滞在が狙える物件のみを優先する傾向が強い。
今後、物件オーナーが取るべき選択肢とは?
● 自主管理への移行を検討
代行会社が受けてくれない場合、自らホストとして管理業務を行うことも視野に入る。ただし、清掃やゲスト対応、価格調整のノウハウが求められるため、現実的には難易度は高め。
● 中小・地域密着型の代行会社を探す
大手代行会社が断る物件でも、地域に根ざした小規模代行業者であれば引き受けてもらえるケースもある。手数料がやや高めになることもあるが、柔軟な対応が期待できる。
● 物件のリノベーション・コンセプト見直し
思い切って内装や設備をアップデートし、”滞在価値”を高めることで再び収益性を上げられる可能性がある。特に「地域の文化を感じられる空間」「ペット可」「ワーケーション対応」など、特定ニーズに応える設計が有効。
結論:民泊は“誰でもできる”時代を終え、選ばれる物件・選ばれるホストへ
民泊は低コストで始められる副業、というイメージが強かった時期もある。しかし今や、宿泊業としての本質が問われるフェーズに入っており、収益性・運営効率・顧客満足度をすべて成立させる必要がある。
運営代行会社も、限られた人員と資源を「利益が出る物件」に集中させるのは当然の戦略であり、今後この傾向はさらに強まるだろう。
逆に言えば、「選ばれる物件」になるためにどのような魅力を備えるか。その戦略こそが、これからの民泊運営における鍵となる。