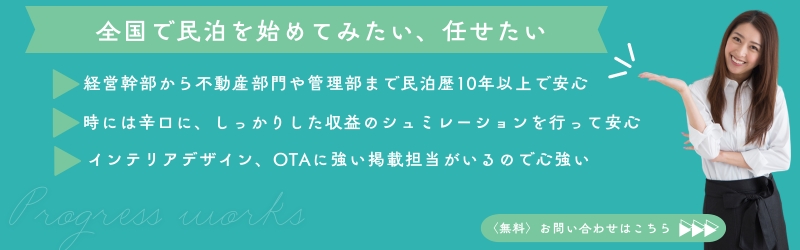不動産業と民泊運営は協業できるのか?──収益の最大化を狙う両者の接点と課題
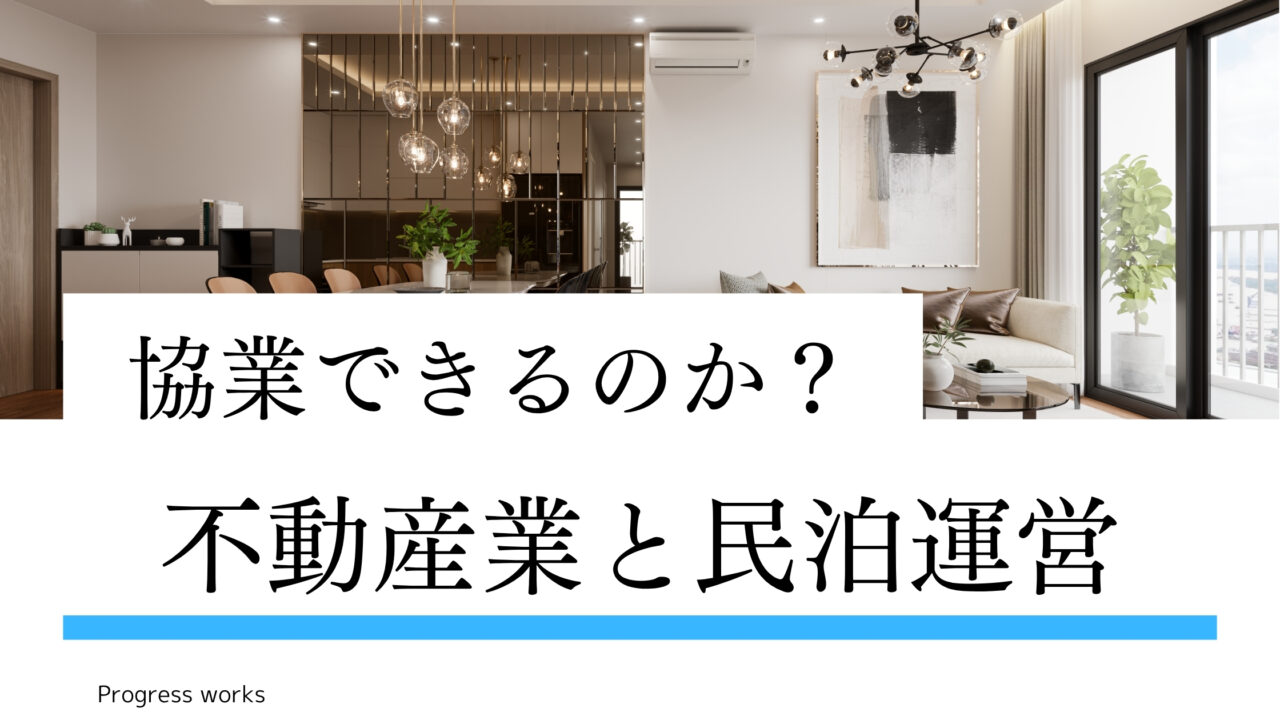
空室率の上昇、賃貸市場の競争激化、建物の老朽化──
そんな課題に直面している不動産業界において、**「民泊との連携」**は新たな収益機会として注目されています。一方、民泊運営者(ホスト)にとっても、良質な物件確保やスムーズな契約・管理を実現するためには、不動産業者との連携が不可欠です。
では、不動産業と民泊運営は本当に“協業”できるのでしょうか?
本コラムでは、両者の視点からメリットと障壁、協業の可能性を深堀りし、今後の展望について考察します。
■ 不動産業が抱える「空室リスク」と民泊の可能性
日本の賃貸市場では、少子化と都市一極集中により、地方や郊外の空室率が深刻化しています。築年数が経過した物件は、通常の賃貸では入居者がつかず、オーナーからの管理手数料収入も頭打ちになりやすい状況です。
一方、民泊は「短期・中期での貸し出し」によって、
-
高い稼働率を維持しやすい
-
賃料よりも高い収益が見込める
-
空室期間を減らせる
といった点で、不動産オーナーにとっての代替的な収益モデルになります。
そのため、不動産業者が自ら民泊運営に乗り出すケースも増えつつあります。
■ 不動産業と民泊運営、協業の5つのモデル
ここでは、実際に行われている協業パターンを紹介します。
① 不動産会社 × 民泊運営代行会社
物件紹介+契約+管理は不動産業者が担当し、運営(清掃、ゲスト対応、OTA管理など)は外部の民泊代行会社が請け負う形。初期投資やリスクを分担できるため、協業モデルとしては最もポピュラーです。
② 不動産会社が民泊運営部門を内製化
不動産会社が自社で民泊事業部を立ち上げ、自ら運営まで行うモデル。すべて社内で完結する代わりに、人材・ノウハウ・システム整備などのハードルが高い。
③ 民泊ホストと提携して物件開拓(マッチング型)
民泊運営者が物件を探しており、不動産業者が**「民泊可能な物件」を提供する形**。両者で収益を分け合う、または紹介料モデルを採用するなど。
④ サブリース × 民泊
不動産業者やホストが物件を借り上げたうえで、民泊として運用する形。家賃保証と民泊収益をバランスさせることが求められるため、契約設計が非常に重要。
⑤ リノベーション × 民泊 × 不動産再販
古い物件をリノベ+民泊実績付きで販売するという再販モデル。投資家向け商品として企画されるケースが多く、不動産業者の収益源として注目されています。
■ 協業によるメリット
◎ 不動産業側のメリット
-
空室物件の新たな収益化手段を得られる
-
投資家へのアピールポイントが増える(利回り提案)
-
家賃収入よりも収益性が高いモデルを扱える
-
民泊市場に参入することで新規顧客(インバウンド投資家など)との接点が増える
◎ 民泊運営側のメリット
-
物件の紹介・契約サポートを受けられる
-
管理会社との連携が取りやすくなる(ゴミ出し、近隣対応)
-
エリア情報、建物構造などの専門知識を活用できる
-
法令対応(用途地域、条例、建築基準)の確認がしやすい
■ 協業の障壁・課題
協業には多くのメリットがある一方で、明確な「摩擦点」も存在します。
× 民泊に対する理解不足
不動産業者側が民泊の運営実態や収益モデルを理解していないことが多く、表面的に“怪しい”という印象で敬遠されるケースも。
× 管理会社とのトラブル
多くの管理会社は、「民泊禁止」条項を入れているため、勝手に民泊を行うと法的トラブルに発展するリスクあり。事前の合意形成が不可欠です。
× 利害のズレ
不動産業者は「安定した家賃収入」、民泊運営者は「収益最大化」を狙うため、利益の基準がズレて交渉がまとまらないことも。
× 法的ハードル
用途地域、消防法、建築基準法、条例など、民泊が合法に運営できるかどうかは非常に複雑な判断が必要。不動産業者が慎重にならざるを得ない理由のひとつです。
■ 今後の展望:共通言語と“第三者の翻訳者”がカギに
不動産業と民泊運営が協業していくには、お互いの専門性を尊重しながら、共通言語での意思疎通ができる関係性が求められます。
実務的には、
-
「民泊に詳しい不動産営業」
-
「不動産に詳しい民泊運営者」
-
「両者を翻訳できる第三者(コンサル・PM)」
といった**“橋渡し役”が不可欠**です。
また、不動産業界の中でも「遊休不動産」「相続案件」「地方物件の活用」などに対して、民泊という選択肢が市民権を得てきている今、協業のニーズとチャンスは間違いなく増えています。
■ 結論:「協業」は可能。ただし“学び合う姿勢”と“戦略的設計”が必要
不動産業と民泊運営は、共通の目的(物件を活かして収益を上げる)を持ってはいますが、言語も文化も異なる業界です。
だからこそ、互いの強みを活かして、
-
役割分担
-
リスク設計
-
成果分配
-
合法性の担保
をしっかり定義できれば、双方にとって「持続可能で、収益性の高いビジネスモデル」になる可能性は十分にあります。
「民泊は不動産業の“敵”ではない」
むしろ、これからの不動産業が生き残るための**“味方”になり得るパートナー**なのです。