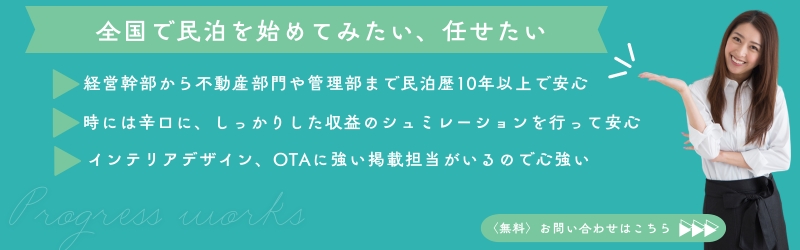「モームリ、民泊やめたい」──それでも“やめられない”民泊運営の重さと覚悟

■ 「空室活用で副収入」──甘いイメージの裏にある現実
最近ではSNSやYouTubeで「空き部屋で副収入!」「月10万円の不労所得!」といった、民泊ビジネスの“キラキラ系成功ストーリー”が数多く発信されています。
確かに、うまく回せばそれなりの収益も出る。
しかし、現実の民泊運営は想像以上にハードで、気軽な副業などでは到底ないというのが、多くの運営者が口をそろえて言う真実です。
そして多くのホストが一定期間運営したのちに、こうつぶやきます。
「モームリ。やめたい…」
でも、そのときになってようやく気づくのです。
「民泊って、やめるのもめちゃくちゃ大変だということに」
■ 民泊が“やめられない”3つの理由
① 【未来の予約】が数ヶ月先まで入っている
民泊は基本的にOTA(AirbnbやBooking.comなど)を通じて中長期的に予約が入り続けます。
「もう限界だから明日からやめよう」と思っても、既に半年後、1年後の予約が確定している場合もあるのです。
キャンセルするには、
-
ゲストに謝罪連絡
-
キャンセル料の負担
-
OTAからのペナルティ(評価低下・掲載停止)
が発生します。悪質なキャンセルと判断されれば、ホストアカウントが強制停止されるリスクもあります。
② 登録・許認可の関係で「一時停止」すら難しい
民泊を始めるには、以下のいずれかの許可・届け出が必要です:
-
旅館業(簡易宿所)許可
-
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)
-
特区民泊
これらはいずれも、定期的な営業報告・宿泊者名簿の保管・緊急時の対応義務を伴います。
「やっぱやめます」と届け出を出すだけでは済まず、
-
自治体との手続き
-
現在の予約終了の確認
-
法人登記や管理委託契約の精算
-
ホストアカウントの停止処理
など、意外と“やめるための事務処理”に膨大な手間と時間がかかるのです。
③ 周辺住民や管理会社への説明責任
集合住宅の場合、「管理組合との取り決め」「近隣トラブル対応」が絡みます。
「やめたいから放置」は、ご近所トラブル→苦情→行政指導に発展しかねません。
また、運営代行会社と契約している場合は、最低契約期間・解約金の発生もあり得ます。
「収益が落ちたから、解約」は通用しない場合が多く、精神的にも金銭的にも引き止め要素になります。
■ 「民泊やめたい」と思う主な原因
以下のような理由で疲弊していくホストは非常に多いです:
-
清掃や備品補充の手間に疲れた
-
トラブル(騒音・ゴミ出し・鍵紛失)対応に追われる
-
ゲストからの理不尽なクレーム
-
近隣住民や管理組合からの圧力
-
利益が出ない(赤字続き)
-
AirbnbやBooking.comの仕様変更に振り回される
-
稼働が下がっても、家賃やローンの支払いが固定費として残る
こうした「消耗とストレスの積み重ね」が、やめたい気持ちにつながっていきます。
■ 始める前に知っておくべき「覚悟のリスト」
民泊を始める前に、本当に理解しておくべき現実があります。
✅ 最低でも半年先までの運営責任を背負うことになる
✅ やめるにも手続きと調整が必要で、簡単には逃げられない
✅ 副業ではなく、“宿泊業”としての義務と覚悟が求められる
✅ 収益が出るようになるまで半年~1年かかることもある
✅ トラブル対応はほぼ24時間体制(鍵、騒音、電気、Wi-Fi…)
✅ 悪質ゲストに泣き寝入りするケースも少なくない
これらを**「自分の責任として受け止める覚悟」がなければ、民泊運営は非常にしんどい選択肢**です。
■ 「気軽に始められるけど、気軽にはやめられない」のが民泊
民泊というビジネスモデルは、たしかに低資本で始めやすく、魅力的に見えるかもしれません。
でもその分、“出口”が非常に狭く、逃げ場がないのです。
副業のつもりが、本業以上に疲弊してしまったホストは決して少なくありません。
■ 終わりに:それでも始めるなら、覚悟を持って「準備と設計」を
民泊をやめるのが難しい最大の理由は、最初から“やめるとき”のことを想定していないからです。
だからこそ、これから民泊を始めようと思っている人には強く伝えたい:
● いつでも撤退できるよう、契約・運営・資金を設計しておくこと
● 未来の予約が命綱にも首輪にもなりうること
● 「もう無理」と思った時に備えて、代行や引継ぎの選択肢を持つこと
民泊は「空き部屋活用」ではなく、立派な宿泊事業です。
始めるときにこそ、“やめる時のリスク”を理解し、覚悟を持つ必要があります。