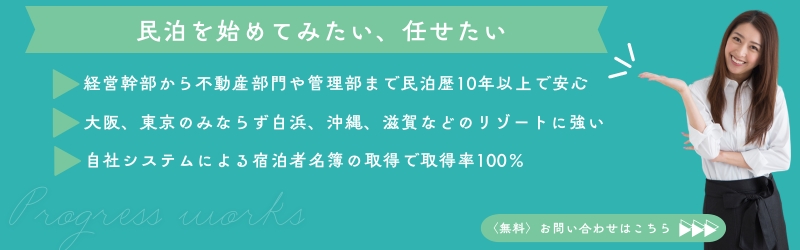「ホテル vs 民泊」はもう古い──比べるものではなく、“選ばれる理由”が違うだけ
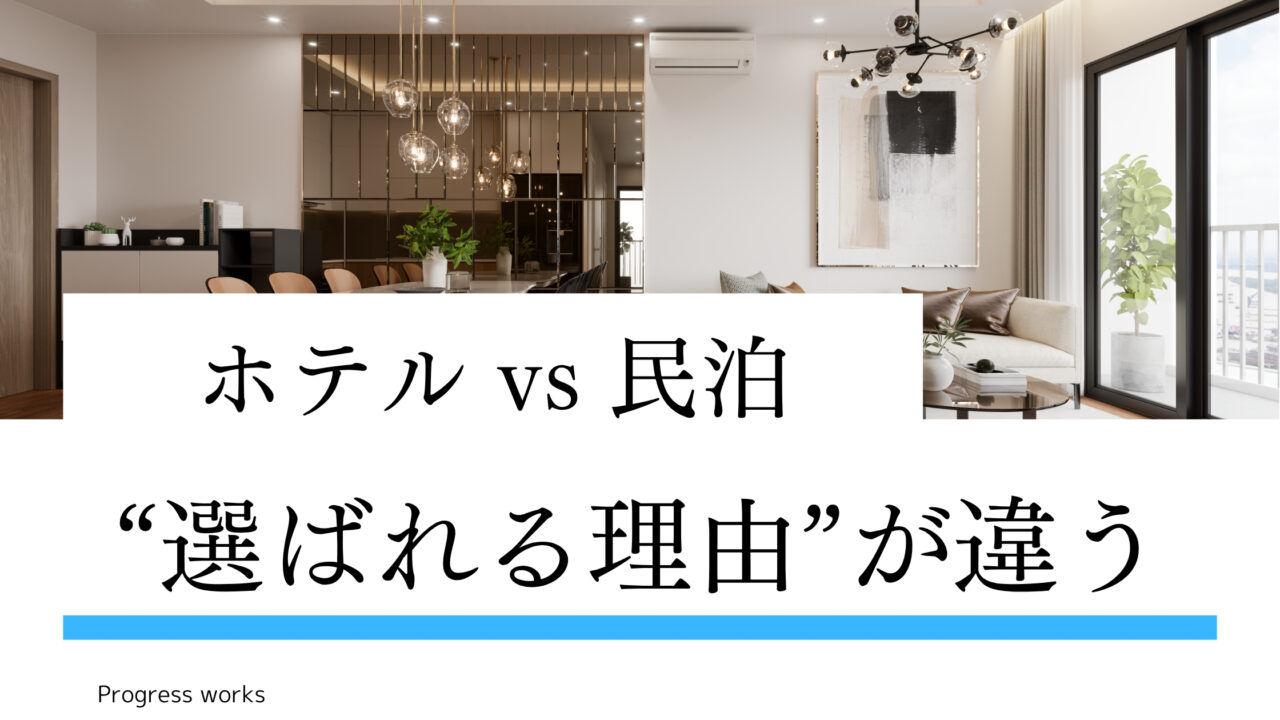
■ 「ホテルと民泊はライバルだ」と思っていませんか?
よく耳にします。
「民泊がホテル業界の脅威になっている」
「ホテルが価格を下げざるを得なくなった」
「民泊のせいで宿泊業界が崩壊する」
確かに、民泊や貸別荘が台頭したここ10年で、
宿泊の選択肢は一気に広がりました。
しかしそれは、「どちらかが正解で、どちらかが間違い」という話ではありません。
むしろ本質はこうです。
ホテルにも民泊にも、それぞれの“強みと目的”があり、共存できる存在であるということです。
■ 実は“求められていること”がまったく違う
ホテルが求められている理由:
-
スタッフ常駐による安心感とサービス
-
アクセス重視の都市型立地
-
食事付き・アメニティ完備などの利便性
-
法人・ビジネス利用者の定番宿泊先
民泊(マンション型・一軒家型)が選ばれる理由:
-
キッチン・洗濯機付きの生活体験型ステイ
-
複数人・家族旅行でのコスパ重視の宿泊
-
ちょっとディープなローカルエリアの滞在
-
ホテルにはない個性的な内装・空間
貸別荘(ヴィラ型)が好まれる理由:
-
ペット同伴やBBQ可など自由度の高さ
-
グループ旅行や親族旅行でのプライベート空間確保
-
自然に囲まれた非日常の体験価値
-
長期滞在・ワーケーションに最適な静けさと広さ
つまり、選ぶ理由がまったく違うのです。
宿泊施設=すべて代替可能なライバルという前提自体が、もう時代遅れなのです。
■ 実際の利用者は“目的”で宿を使い分けている
旅行者のリアルな動きは非常に現実的です。
-
「今回はビジネス出張だからホテル」
-
「家族で旅行だから、民泊にしよう」
-
「友達とのグループ旅行は貸別荘がいいよね」
-
「おじいちゃんも一緒だから温泉旅館にするか」
人は、価格や立地だけでなく、シーンや目的に応じて宿を使い分ける時代に入っています。
“選ばれる宿”であるかどうかは、用途と体験価値にフィットしているかどうかにかかっているのです。
■ ホテルにできて、民泊にできないこと(そしてその逆も)
ホテルにしかできないこと:
-
深夜到着・早朝出発などへの対応力
-
毎日清掃があり、管理体制が整っている
-
コンシェルジュやフロントスタッフによるサービス
-
法人契約など、ビジネス利用に最適化されている
民泊・貸別荘だからこそ提供できる価値:
-
自炊ができる、洗濯もできる、暮らすように滞在できる
-
旅館やホテルでは不可能な大人数での1室利用
-
ペット同伴や子どもの騒音などにも寛容
-
地元ならではの文化体験や地域密着のローカル滞在
どちらかが上で、どちらかが下という話ではありません。
提供している価値とコンセプトがまったく違うのです。
■ 「棲み分け」こそが、宿泊業の未来
いま日本の宿泊業界に必要なのは、不要な敵対視ではなく、棲み分けと共存です。
ホテルは「安心・安全・信頼・利便性」で選ばれる。
民泊・貸別荘は「体験・自由・非日常」で選ばれる。
そして、どちらにも共通するのは、
ゲストに“選ばれる理由”を明確に伝える努力です。
■ “競合”ではなく“選択肢”になろう
これからの宿泊業において、民泊・貸別荘はホテルの代わりになるのではなく、
もう一つの「選択肢」として価値を発揮することが求められています。
民泊のホストがホテルのようなサービスを求められる場面もあります。
ホテルが地域体験を提供するようになってきた背景もあります。
しかし、それはお互いが“進化”し、“歩み寄る”ことであり、
敵対ではなく、役割を補完し合う構造が生まれているのです。
■ 最後に:宿泊体験は“人”によって意味が違う
-
一人旅で「とにかく静かに休みたい人」
-
家族連れで「キッチン付きがありがたい人」
-
仲間とワイワイ過ごしたい「学生グループ」
-
テレワークで2週間滞在する「ワーケーター」
彼ら全員に「ホテルが最適」ではないし、
全員に「民泊が正解」でもない。
正解はただ一つ、“その人の旅の目的に合った宿泊”なのです。