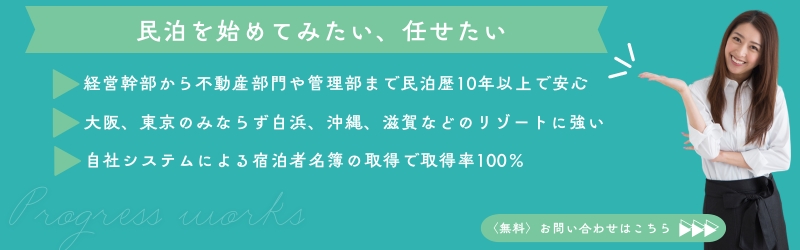【コラム】「うちの施設じゃないんです」──大阪・民泊ラッシュの裏で、現場を疲弊させる“間違いゲスト”の連絡地獄

最近、大阪で起きている“民泊ラッシュ”は、表面上は明るいニュースに見えるかもしれません。
確かに、インバウンドの回復と万博効果で街は活気づき、空き物件を使った民泊の開業が急増しています。
しかしその一方で、我々のような運営歴の長い民泊会社が、**「自分たちと無関係のゲスト」**からの連絡に日々振り回されている現状をご存知でしょうか?
本日は、あえて声を上げさせていただきます。
「すみません、玄関の鍵が開かないんですが…」──でも、そのゲスト、うちの宿泊者じゃありません
ここ最近、我々の**緊急窓口にかかってくる電話のうち、約3割が“別施設のゲストからの誤連絡”**です。
たとえば、ある日の深夜0時過ぎ。
焦った様子の外国人ゲストから「いま宿に着いたがドアが開かない」と連絡が来ました。
名前を聞いても予約履歴はなし。部屋番号を尋ねると、うちが管理していないフロア。
よくよく話を聞けば、同じ建物内で別の事業者が運営している施設への宿泊だったのです。
そしてこれは、珍しい話ではありません。
毎日のように発生しています。
説明しても納得されない。「でもメールにこの住所って書いてあった」
この手のトラブルで最も厄介なのが、「うちの施設ではない」と説明しても、すぐに納得してもらえないことです。
ゲストは「住所がここだと書いてある」「写真と建物が一致している」と言って譲りません。確かに住所は一致している──でも、この建物には複数の民泊事業者が入っているんです。
ゲストは旅行疲れと不安で冷静ではないことも多く、言葉が通じにくい中で、粘り強く説明し、確認し、正しい施設に誘導する。
本来の我々のゲストでもない方に対して、数十分かけて対応を行うのが、最近ではもはや日常業務の一部と化しています。
トラブルの原因は「慣れていない新規オーナー」と「不完全な案内」
こうしたトラブルの大半は、最近参入した民泊オーナーや運営会社による案内の不備・不親切さが原因です。
-
メールに記載されている住所が曖昧
-
鍵の受け渡し方法がわかりづらい
-
建物の写真が違う施設と似ている
-
フロアや部屋番号の表記ミス
-
チェックイン方法がPDF添付で説明されているが、ゲストはそもそも開いていない
さらには、トラブル時にその施設の連絡先につながらない、応答がない、海外在住オーナーで時差対応、など…。
そのツケが、我々“関係のない施設”に回ってきているのです。
我々の負担はタダではない。リスクと誤解も背負っている
当然ながら、そういったゲスト対応に追われれば、本来自社のゲストへの対応が後回しになります。
また、無関係なゲストが勝手にうちのドアの前に立っていたり、他のゲストに話しかけたりすることで、「なんか落ち着かない宿だった」とネガティブなレビューがつくリスクさえあります。
間違えて来たゲストが「ここのスタッフ冷たかった」と感じてしまえば、GoogleレビューやOTAレビューに低評価を書くこともある。
運営側が丁寧に説明しても、相手の感情次第で評価は下がってしまう。それが現実です。
真面目に運営している我々が、なぜここまで負担を背負わなければならないのか
民泊は「誰でも始められる」と言われています。でも、それは「誰でも適切に運営できる」こととは違います。
不慣れな事業者が不十分な案内で民泊を始め、そのしわ寄せが別の運営会社に行くという構造は、業界全体の信頼を損ない、長く続けてきた運営者ほど不利になるという本末転倒な状況を生み出しています。
業界全体での「仕組みづくり」が求められている
このままでは、真面目に運営している会社ほど疲弊し、結果として民泊そのものの信頼が崩れていきます。
以下のような制度・対応の導入が、いま本気で求められています:
-
同じ建物内での「施設名かぶり」を避ける規制
-
初心者オーナーへの案内テンプレート義務化
-
施設ごとの連絡先・緊急窓口の一元化
-
チェックインガイドに写真+地図+建物全体の案内図を必須化
-
プラットフォーム側での予約画面のUI改善(Googleマップ誤誘導対策)
最後に:もう一度、“ゲスト体験”の本質を考えてほしい
民泊運営において、鍵の受け渡しや施設案内は単なる作業ではありません。
それは、ゲストの「旅の第一印象」をつくる、最初のホスピタリティです。
慣れていない運営者が、適当に案内を済ませ、トラブルが起きても「他人事」でいるなら、いずれそのゲストは二度と民泊を使わないでしょう。
そして、その悪印象はなぜか無関係の我々の施設にまで降りかかってくるのです。
民泊の未来のためにも、“開業するだけ”ではなく“責任を持って運営すること”の大切さを、今こそ業界全体で再確認すべきではないでしょうか。