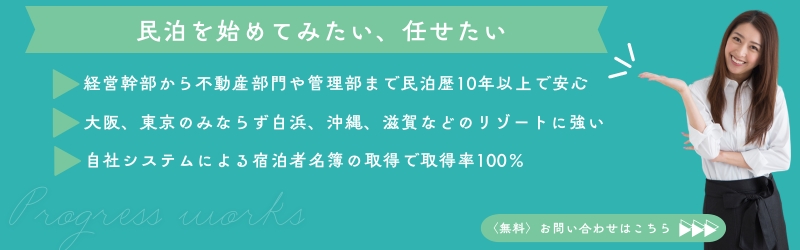そのゲスト、本当に“旅行者”ですか?──民泊に潜む悪質ゲストと年々高まるリスクへの対策

かつて「空き家活用」や「副収入の柱」として注目を集めた民泊。
AirbnbやBooking.comなどOTA(オンライン旅行代理店)の普及により、今や民泊は“個人が気軽に宿を始められる時代”となった。
しかしその裏で、民泊が持つ「監視の緩さ」や「匿名性の高さ」が、悪質ゲストの温床になりつつあることをご存じだろうか?
近年、宿泊業界では**「犯罪に使われた」「備品が盗まれた」「言いがかりで訴えられそうになった」**というような、悪質ゲストに関する報告が急増している。
これは単なる“マナーの悪さ”の話ではない。
犯罪と詐欺の現場にされるリスクが、今、あなたの宿に忍び寄っている。
民泊が「潜伏・犯罪拠点」に使われる時代
警察庁や複数のメディアでも報道されている通り、最近では**「振り込め詐欺の拠点」として民泊が使われるケース**が確認されている。
-
携帯電話を大量に持ち込んで“掛け子”として連日活動
-
宿泊者が何人も出入りし、近隣から不審通報が入る
-
滞在後、部屋にプリンターや犯罪メモ、SIMカードが放置されていた
これらは、実際に民泊オーナーが経験した事例の一部に過ぎない。
民泊はホテルとは異なり、チェックインの顔確認が甘い、スタッフが常駐していない、**室内に監視カメラがない(設置禁止)など、「誰が何をしていたか分からない空間」**になりやすい。
その匿名性の高さこそが、悪質ゲストにとっての「使いやすさ」でもある。
備品の持ち去り・部屋の破壊…“モラル崩壊型ゲスト”も増加
犯罪利用だけでなく、「備品の持ち去り」や「室内破損」を故意に行うゲストも後を絶たない。
▽ よくある被害例
-
バスタオルや寝具、調理器具の持ち帰り
-
高級チェアや装飾品のすり替え
-
壁紙の破れ、家具破損、窓の開けっぱなし退室
-
電子レンジや冷蔵庫を壊して弁償せずチェックアウト
しかも、こうした被害に対してOTAに報告しても、**「チェックイン時の写真はあるか」「現場証拠はあるか」**といった形式的なやり取りで終わってしまうことも多い。
個人オーナーの場合、被害の泣き寝入りは珍しくない。
「盗まれた」と言いがかりをつける“逆詐欺型ゲスト”の存在
さらに厄介なのが、「部屋に置いていたはずのものが盗まれた」と宿側に言いがかりをつけるケースだ。
-
「現金がなくなった」
-
「高級時計を置いていたのにチェックアウト後に気づいた」
-
「スタッフが盗んだのでは?」
こうした主張がOTAに通報されると、事実確認もないまま宿の掲載停止やアカウント停止処分が下されるリスクすらある。
当然、室内に防犯カメラを設置することはプライバシーの問題で不可。
証明する手段がない中で、ゲストの一方的な主張が優先される場面もあり、オーナーにとっては極めて不公平な立場となる。
個人オーナーが狙われやすい時代になっている
SNSや掲示板、暗号化チャットなどでは、**“個人運営の民泊は騙しやすい”**といった不穏な情報が出回っている。
-
チェック体制が甘い
-
顔出しせずに泊まれる
-
トラブル対応が遅い
-
弁護士がいないため強く出れば引き下がる
こうした情報を頼りに、意図的に個人オーナー運営の宿を狙うゲストが存在するのが現実だ。
OTAは守ってくれない。“自己防衛”がすべて
多くのオーナーが誤解しているのが、「OTAが何とかしてくれる」という期待だ。
しかし、実際にはプラットフォームは“中立”であることを建前としており、オーナー保護に動くことは極めて少ない。
被害報告をしても、
-
“宿とゲストの間で話し合ってください”
-
“返金対応は当社では行いません”
-
“証拠が不十分なため対応できません”
という冷たいリアクションで終わるのがほとんど。
自分の施設と収益は、自分で守るしかない。
対策①:顧問弁護士との契約は「保険」ではなく「盾」である
実際に、悪質ゲスト対応や被害請求を想定して、顧問弁護士を契約する宿オーナーが増加中だ。
-
宿泊契約の細かい文言の整備
-
トラブル時の通知・警告文の作成
-
損害請求の代理交渉
-
法的に有効な証拠の確保アドバイス
など、弁護士が「いる」だけで、オーナーの立場は圧倒的に強くなる。
「法的対応も視野に入れています」と一言添えるだけで、軽視されやすい個人オーナーでも、舐められずに済む環境を整えられる。
対策②:ゲスト評価の事前チェック・ブラックリスト共有
一部の運営会社や民泊グループでは、**“過去にトラブルを起こしたゲストの情報共有”**を行っている。
自社予約システムやDMを活用して、危険人物のチェックや入室制限を行うことが、リスクの一次防衛策となる。
また、チェックイン時の本人確認や、事前質問によるコミュニケーションで「怪しい兆候」を察知するスキルも求められる。
対策③:運営代行会社を介した“フィルター”運営も選択肢
もし自分ですべてのリスクに対応するのが難しいなら、
信頼できる運営代行会社に委託するというのも有力な選択肢だ。
-
清掃スタッフによる現地の異常報告
-
弁護士・保険会社との連携
-
ゲスト対応マニュアルの徹底
-
被害時の立証・交渉ノウハウ
こうした“セーフティレイヤー”が厚くなることで、宿が危険にさらされる頻度も大きく下がる。
結論:民泊運営は、“戦える体制”を持っているかどうかがすべて
民泊は、誰でも始められる。
だが、「誰でも守られる」わけではない。
犯罪に使われ、備品を盗まれ、言いがかりで追い込まれ…
そんな悪質ゲストの攻撃に対して無防備でいる限り、個人オーナーは狙われ続ける。
-
顧問弁護士との契約
-
契約書の整備
-
清掃会社・運営会社との連携
-
OTAに依存しない自衛体制の構築
これらは、**“大げさな備え”ではなく、“身を守るための最低限の武装”**だ。
民泊の自由さを楽しむためには、まず“悪意から守る壁”を築いておくこと。
それが、2025年以降の健全な宿運営には欠かせない。