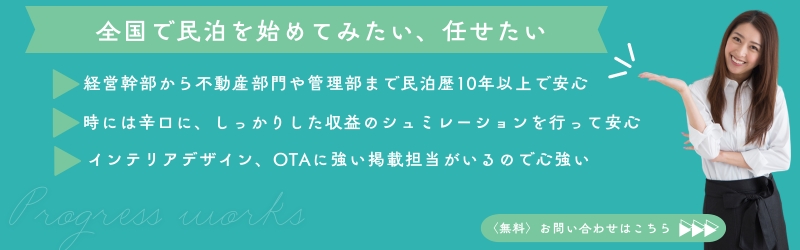【速報コラム】大阪市・特区民泊が新規受付一時停止へ?──申請ラッシュの8月、駆け込み申請は間に合うのか

2025年夏、民泊業界に激震が走っています。
大阪市が進める「特区民泊制度の新規受付を一時停止する方向で調整中」との情報が関係者の間で広がりつつあります。これに伴い、8月に駆け込みで申請を希望する動きが急増しており、現場はすでに混乱の兆しを見せています。
そしてこの動きを裏付けるように、大阪府の吉村洋文知事は、今月の定例記者会見で「新規の(事業申請)募集は停止すべきだ」と明言しました。
これは単なる噂や業界内の憶測ではなく、行政トップが公の場で表明した政策意向です。今後の正式な受付停止へと現実味を帯びた動きといえるでしょう。
このコラムでは、制度の基本から最新状況、駆け込み需要の実態、そして今後を見据えた対応まで、深く掘り下げてお届けします。
特区民泊とは何か?簡易おさらい
「特区民泊」とは、国家戦略特区制度に基づいて各自治体が独自に運用している制度で、本来は旅館業法上の営業許可が必要な短期宿泊施設を、2泊3日以上という制限付きで、比較的簡易な手続きで運営できる仕組みです。
大阪市はこの制度を2016年から導入し、インバウンド観光の波に乗って都市型民泊の主流として多くの物件がこの制度を利用してきました。
一時停止の背景:制度の人気と行政の対応限界
では、なぜ今になって新規受付を止める動きが出てきているのでしょうか?
背景には、以下のような複合的な事情があります。
-
特区民泊の需要急増:インバウンドの回復により、宿泊需要がコロナ前水準を超える勢いで回復中。
-
行政リソースの逼迫:認定には書類審査・現地確認・近隣掲示のチェック等、多くの工程が必要。申請数の増加により処理能力が限界に達している。
-
地域住民との摩擦:無人運営施設の増加により、騒音・ゴミ出し・マナー問題への苦情も増加中。
-
2025年万博を控えた都市環境の整備:治安・環境整備を優先する市の姿勢が強まり、民泊の新規流入を一時的に抑制する狙い。
大阪市は現在、新たな認定受付を「当面停止」することを視野に入れて内部調整に入っていると見られます。正式発表はまだ出ていないものの、すでに行政窓口でのヒアリングでも「今後の受付停止の可能性」を匂わせる場面が増えています。
そして何より今回の動きを本格化させたのが、大阪府知事・吉村洋文氏の発言です。
「これ以上の拡大は避けるべき。新規の(事業申請)募集は停止すべきだ」
(2025年7月 大阪府定例記者会見より)
この発言は、市単位だけでなく府全体としても民泊制度の見直しを進めていく姿勢を示したものであり、制度そのものの潮目が変わることを意味しています。
駆け込み申請が8月に集中中、でも「間に合わない可能性」も?
このニュースを受けて、8月に入り駆け込みでの申請依頼が急増しています。
行政書士、建築士、設計会社、消防設備業者、不動産オーナーなど、関係者の間ではすでに「申請ラッシュ」の兆候が出ており、一部では提出後の現地確認をしていただくための予約申請まで2か月以上待ちというケースも報告されています。
さらに、特区民泊の認定には以下のようなプロセスが必要となります:
-
図面作成、用途変更の要否確認
-
消防署との協議・届出
-
建築基準法上の確認
-
近隣掲示(7日間)とその後の報告
-
市への申請・審査・現地確認
-
認定通知の発行(最短でも申請からおおよそ3週間)
これらの工程をすべてこなすには、実質的に2〜3ヶ月かかるのが通常です。
そのため、「8月中に準備を始めても、9月上旬に決定される可能性のある受付停止に間に合わない可能性がある」という厳しい現実も見えてきました。
特区民泊には更新制度なし――一度取得すれば継続可、だが廃止はリスクに
ここで重要な制度上の特徴があります。
それは、「特区民泊には更新制度が存在しない」という点です。
つまり、一度認定を取得すれば、その物件を使い続ける限り有効です。年ごとの更新手続きは必要ありません。
しかし、逆にいえば一度認定を廃止してしまえば、再認定はできなくなる可能性があるというリスクもあります。
とくに、今後制度が見直され、新規受付が本格的に停止された場合、「戻ろうとしても戻れない」ケースが起こり得るのです。
これからの戦略:「申請できるうちに取っておく」か、「別スキームへの移行」か
これまで特区民泊制度は、低コストで柔軟な運営が可能な“穴場”の選択肢として広く支持されてきました。
しかし今後は、以下のような新たな判断軸が求められるようになるでしょう。
-
今のうちに特区民泊認定を取ってしまい、「権利」を確保しておく
-
今からでは間に合わないと判断し、「簡易宿所」や「住宅宿泊事業(民泊新法)」での運営にシフトする
-
2025年万博終了後を見据えて、戦略的に空室運用・長期貸しへ切り替える
すでに代行業者や行政書士の間でも「申請対応がキャパオーバーに近い」という声が相次いでおり、今後は“選ばれた物件・オーナー”だけが滑り込める状況になっていくと予想されます。
まとめ:吉村知事の発言は「最後の警鐘」
大阪市の特区民泊制度は長年、都市型民泊の中心的存在でした。
しかし今や、「新規受付はいつ停止してもおかしくない」というカウントダウンが始まっていると言っても過言ではありません。
そして、吉村知事の「新規申請は止めるべき」という言葉は、単なる意見ではなく、制度見直しに向けた政治的決断の予告です。
-
一時停止が本決まりになれば、再開の見通しは不透明
-
更新制度がないため、一度逃せば「二度と戻れない」可能性も
-
今から動いても、すでに申請混雑の影響で間に合わない物件も多い
「取れるうちに取る」か「別の道を探すか」――
この判断に、あと何週間の猶予があるのかすら不明な状況です。
情報を集め、今すぐ動くことが求められています。