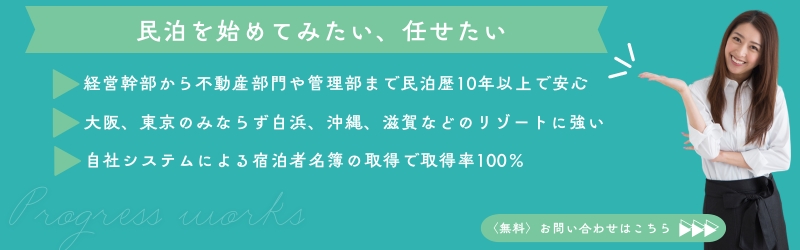【民泊・貸別荘運営の落とし穴】緊急窓口「だけ」の委託がなぜおすすめできないのか?

ここ数年、日本各地で急増している「民泊」や「貸別荘」ビジネス。特に地方や観光地では、空き家の利活用や投資対象として注目を集め、多くの事業者が参入しています。その中でよく聞くご相談のひとつが、「緊急窓口対応だけを外部に委託したい」というものです。
一見、合理的な選択肢にも見えるこの運営スタイル。しかし、実際の現場や業界の実情を知ると、緊急窓口だけを外部委託するというのは、非常にリスクの高い運用形態であることがわかってきます。
緊急窓口だけ委託を希望する人の運営スタイル
このような依頼をする方の多くに共通するのは、「緊急窓口ありき」で運営を組み立ててしまっていること。つまり、「何かあったら緊急窓口に任せればいい」「トラブルが起きたら電話して対応してもらおう」と、本来自らが担うべきリスクマネジメントを外注頼みにしてしまっているのです。
たとえば、エアコンのリモコンの場所が分からない、鍵の閉め忘れで現地に誰か行かなくてはならない、水道の元栓の位置が分からない――これらの事象の多くは、事前の備えやマニュアル、写真、案内の工夫でほとんど防げるトラブルばかりです。
弊社のスタンス:緊急窓口に「連絡が来ない」運用こそ理想
弊社では、民泊・貸別荘の運営において**「緊急連絡が来ないように」運営設計を徹底する**ことを基本としています。
具体的には:
-
写真付きのトラブル対応マニュアルを作成
-
室内や機器のトラブルリスクを事前に洗い出して対策
-
トラブル傾向を把握して、ゲスト向けの注意喚起を事前に行う
これにより、弊社が管理している物件は件数が多くても、緊急窓口への連絡件数が極めて少ないという結果につながっています。緊急対応が必要な状態に**「ならないようにする」ことこそが、プロの仕事**だと考えています。
緊急窓口だけ委託を受ける会社は「受け身」スタイルが多い
一方で、緊急窓口対応だけを引き受ける業者は、ごくわずかです。というのも、緊急窓口という業務は、24時間365日対応を求められる極めてストレスフルな仕事だからです。
しかも、「連絡が来ること」を前提にしている管理体制で委託された場合、業者側にとっては常に何が起きてもおかしくない爆弾を抱えるような状況になります。そのうえ、「対応だけでいい」「現地に行ってくれとは頼んでいない」というような依頼主のスタンスが多く、業者側に責任や対応範囲が不明確なことも多いのです。
そのため、引き受けた業者がどれほど真面目であっても、対応が中途半端になったり、最悪の場合は「何もしない」スタイルに終始する可能性もあります。
「緊急窓口だけ」は長続きしない――業者側の疲弊も現実に
ここ1〜2年で、民泊・貸別荘の運営会社や清掃会社は爆発的に増えました。しかしその多くが、サービス体系を整える前に数十件単位で運営を抱えてしまっている状態です。
特に緊急窓口のみの委託業務を請け負っていた業者では、スタッフのストレスと業務の煩雑さにより、数年以内に撤退するケースも相次ぐと見られます。実際、すでに「もうやりきれない」と夜逃げ同然で連絡を絶った事業者も出てきています。
一度でも緊急時に「連絡がつかない」「対応できない」ことがあれば、宿泊施設の評価や再訪率に大きく影響し、最悪の場合、行政処分や掲載停止などのリスクもはらんでいます。
結論:緊急窓口ありきの運営ではなく、「緊急が起きない設計」を
民泊・貸別荘の運営では、「何かあったらどうするか」ではなく、「何も起きないように設計する」ことが何より大切です。緊急窓口対応は、あくまでも最後の砦であり、日々の運営改善の積み重ねこそが最も有効なリスクヘッジです。
「緊急窓口だけを外注すれば安心」という安易な考え方が、長期的には大きな損失を生む――。業界の一員として、現場で積み重ねた実体験をもとに、そう断言できます。