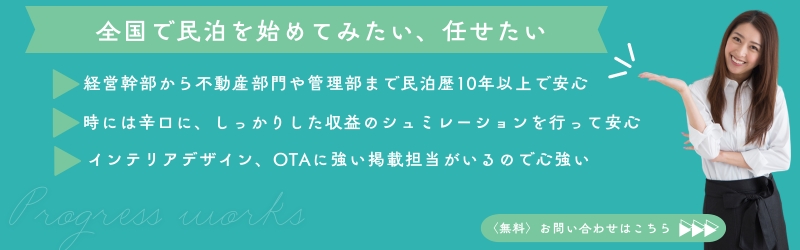【コラム】特区民泊が“ビザ取得の抜け道”に?──大阪市で増えすぎた経営管理ビザ申請者と今後の展望
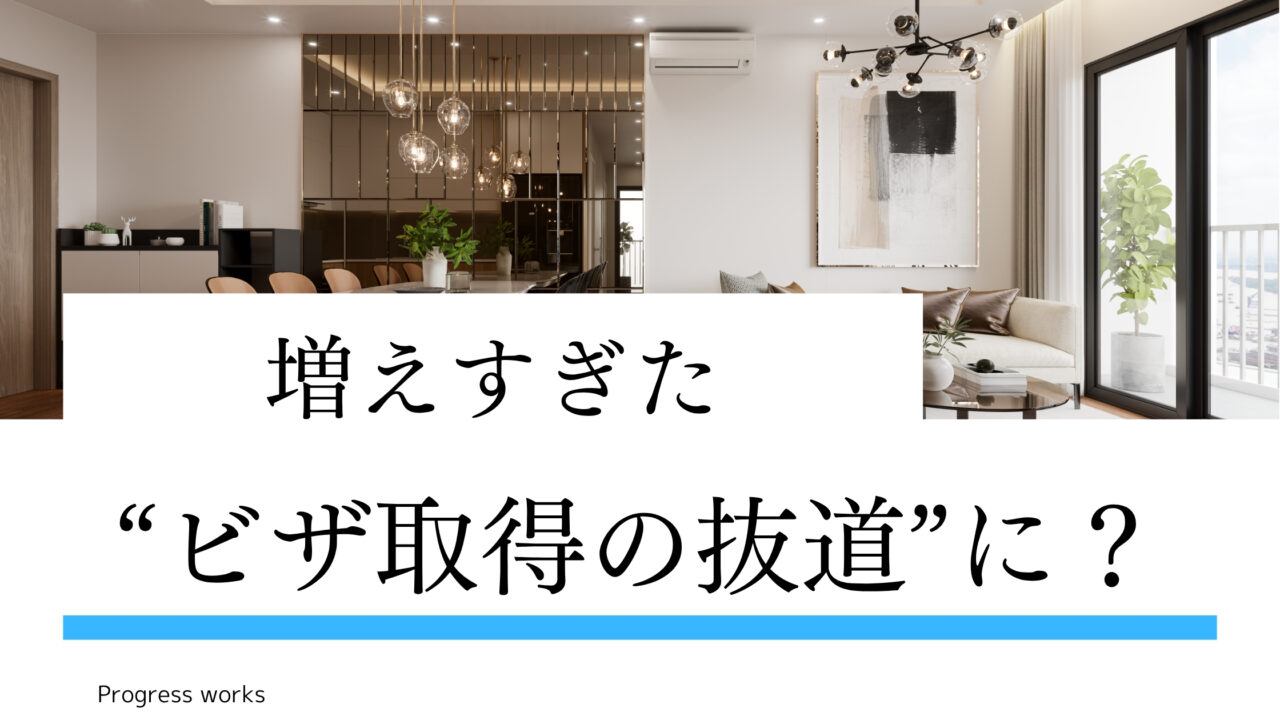
大阪市では近年、特区民泊を活用した外国人による**「経営・管理」ビザの取得申請が急増しており、行政関係者や地域住民の間で懸念の声が高まっています**。
一見、特区民泊と経営管理ビザは無関係のようにも思えますが、実はこの2つを掛け合わせることで、合法的にビザを取得し、日本での長期滞在が可能になる抜け道的スキームが成立しているのです。
この記事では、この構造的問題の実態を掘り下げるとともに、今後の規制強化や業界への影響、そして誠実に運営する民泊事業者がどのような立場に立たされるかについて、詳しく解説していきます。
経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、外国人が日本で事業を開始・管理する目的で取得できる在留資格です。取得には以下のような条件が必要です:
-
日本国内に**事業所(事務所・店舗)**を確保していること
-
事業計画書が現実的かつ継続可能であること
-
投資額(原則500万円以上)があること
-
実際に事業を開始していること など
そしてここで注目されるのが、特区民泊施設も「事業所」として認められる場合があるという点です。
■ 民泊 × 経営ビザ = 抜け道になっている構造とは?
現状、特区民泊は以下のような条件を満たせば比較的簡単に開業できることから、ビザ取得との相性が非常に良いのです:
-
物件取得が容易(特に賃貸契約で代用可)
-
小規模投資でも形にできる(ワンルームでもOK)
-
事業計画書のテンプレート化が進んでいる
-
短期で「事業開始実績」を作りやすい
その結果、「まず特区民泊を届け出 → ビザ申請 → 不稼働・形式的な運営」という**“ビザ取得のためだけの民泊”**が増加。
稼働実績や運営体制がないままの“ペーパー民泊”が乱立する事態になっています。
大阪市での実態:2024〜2025年の動き
特に大阪市では、2024年から2025年にかけて外国籍による新規特区民泊申請数が急増しており、市担当部局にも「明らかにビザ目的と思われる申請」が数多く寄せられているといいます。
また、不動産業者や行政書士が「ビザ取得用パッケージ」として民泊開業一式を売るケースも横行しており、いわゆる「代行屋ビジネス」が活発化しています。
こうした状況を受けて、市や出入国在留管理局、関係省庁が水面下で制度見直しを検討しているとの報道もあります。
今後起こり得る規制強化・行政対応
このままビザ目的民泊が拡大すれば、制度自体が形骸化する可能性が高く、行政が動くのは時間の問題と見られています。予想される対策は以下の通りです:
1. ビザ審査基準の厳格化
-
特区民泊を事業所とする場合、実質稼働・運営体制の証明を必須に
-
稼働実績(宿泊実績数・レビューなど)の提出義務化
-
形式的事業に対する不許可措置
2. 特区民泊届出の要件見直し
-
自主管理が難しい外国人オーナーへの審査強化
-
外国籍法人による届出に対し追加資料の提出要求
-
短期間での転売・譲渡・運営者変更に制限
3. 行政連携の強化
-
大阪市と入管局の情報共有体制の整備
-
民泊届出と在留資格審査を紐づけてチェック
-
地域トラブルが発生した場合の即時報告体制
これらの規制が実施されれば、形式だけの“ビザ用民泊”は淘汰されていくことになるでしょう。
誠実な事業者にとっては“浄化”のチャンス
逆に言えば、こうした規制強化はきちんと現場で運営している民泊事業者にとっては明確な追い風です。
-
周辺に“幽霊民泊”が乱立しないことで、レビュー競争・価格競争が健全化
-
行政の信頼を得やすくなり、補助金・地域連携プロジェクトの対象に
-
市場価値の高い「きちんと稼働している物件」が資産として再評価
現時点で誠実に民泊運営をしている方々にとって、信頼と持続可能性をベースにした“本物の民泊運営”が評価される時代がようやく訪れようとしているのです。
まとめ:ビザ目的の特区民泊乱立は、制度改革の引き金になる
今の大阪市における「ビザ目的民泊」は、制度の盲点を突いたものであり、健全な観光産業の育成にとって大きなリスクです。
しかし、同時にこれは、民泊制度全体の見直しと進化をもたらす「きっかけ」でもあります。
今後、行政が制度の穴を塞ぎ、事業実態のある民泊だけが残るようになれば、真面目に向き合ってきた運営者こそが、信用と収益の両方を手にすることができるでしょう。