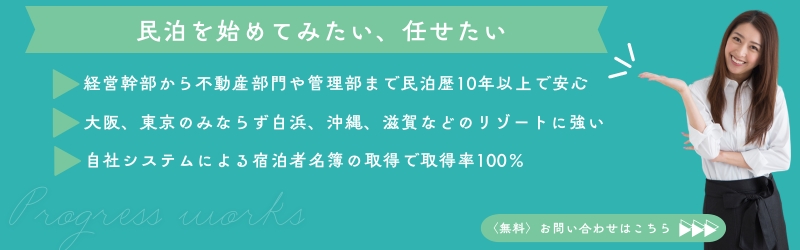苦情対応は「最前線」へ──大阪市の動きが示す、民泊運営における電話対応の本質的な転換

目次
2025年7月25日、大阪市は国家戦略特区法に基づく「特区民泊」に関する運営実態と課題について、対処方針を発表しました。その中で特に注目されているのが、「苦情対応体制の改善」に向けた条例の見直しと、事業者処分の明確化、そして全施設の一斉調査の方針です。
背景には、近隣住民からの騒音・ゴミ出しトラブルなどの苦情が絶えず、それに対する事業者の対応が追いついていないという現実があります。市はすでに、**「実際に苦情窓口として届け出られている電話番号が稼働しているか」「その電話口で日本語による円滑な意思疎通ができるか」**といった具体的な調査に着手しはじめており、今後はさらに踏み込んだ実務レベルの確認が進められることが予想されます。
「その電話、本当に鳴っていますか?」──大阪市が調査を始めた「電話窓口の実態」
今回の大阪市の調査では、事業者が届け出ている苦情対応用の電話番号が本当に通じるかどうかがチェック項目として挙げられています。これは実際に、私がかつて知人に委託していた物件で経験したことと重なります。
当時、管理会社に苦情窓口も委託していたのですが、ある日「近隣住民が電話をかけてもずっと出ない」と市の職員から連絡がありました。調べると、夜間帯の電話は別の外注会社に転送されており、さらにその会社では対応マニュアルが不完全だったため、「日本語での苦情内容を正確に把握できていなかった」ことが判明。結局、運営責任者である私の方に苦情が集中することになったのです。
電話が鳴っても誰も取らなかった。取っても、話が通じなかった。
この2点が重なると、もう「苦情窓口として機能していない」とみなされても仕方ありません。
氏名と電話窓口の「ズレ」も問題に──行政の見ている視点
大阪市は、「届け出された責任者の氏名」と、実際に電話対応をしている人物が一致しているかも調査対象としています。
これはつまり、「形式だけの氏名登録ではなく、実際に責任者本人またはその指導下で、対応が確実に行われているか」という実質運営の確認に他なりません。
民泊や貸別荘の運営では、よく「一部だけ業務を外注して、他は自分たちでカバーする」といった部分委託型のスタイルが採られることがあります。しかし、こうした体制では**“誰が、いつ、どこで、何を対応しているのか”が行政にも把握されにくく、結果として運営責任が不明確になる**という問題が生じやすくなります。
運営体制の見直しを検討すべきタイミング
大阪市の今回の発表は、民泊運営者にとって「電話応対の在り方を見直す決定的な転機」と言えます。これからの民泊・貸別荘運営は、宿泊者とのやりとりや予約処理だけではなく、“行政や地域社会との関係構築”がますます問われる時代に入ったのです。
一部の業務を切り出して「なんとかなる」時代は、終わりを迎えつつあります。これを機に、包括的で責任の所在が明確な運営体制=フル委託型への移行を含めて、今一度自らの運営体制を見直すべき時期ではないでしょうか。