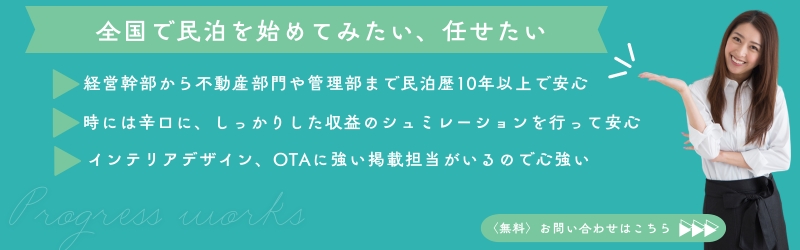「ちょっと焚いただけ」が命取りに――貸別荘と蚊取り線香トラブルの真実

夏の定番、蚊取り線香。でも貸別荘では少しだけ気をつけたい。
「キンチョーの夏、日本の夏」——そんなフレーズとともに思い浮かぶ、夏の虫除けといえば蚊取り線香。
小さな子どもがいるご家族や、虫が苦手な方にとって、安心できる存在かもしれません。でもその一服の煙が、貸別荘という空間では思わぬトラブルを引き起こすことがあります。
蚊取り線香自体が悪いわけではありません。ただ、「場所と方法によっては少し注意が必要になる」というのが、貸別荘という特別な空間の現実なのです。
なぜ蚊取り線香がトラブルの原因になるのか?
蚊取り線香のトラブルは、主に以下の2つに集約されます。
◉ 火災警報器が反応してしまうことがある
貸別荘の多くは、煙に敏感な光電式の火災報知器が備えられています。
室内や風の弱い場所で蚊取り線香を焚くと、その穏やかな煙が警報器に届き、突然の警報音が鳴ってしまうことがあります。
夜間に警報が鳴れば、ゲストも驚きますし、近隣から通報されることも。運営側にとっても、緊急対応や報知器の点検費用など、見えないコストがかかる事態になりかねません。
◉ 焦げ跡や設備破損の原因になることも
屋外で使用した蚊取り線香の置き場所が木製のデッキやウッドチェアの上だったというケースも少なくありません。
金属の受け皿が高温になることで、知らず知らずのうちに焦げ跡や焼け跡が残ってしまうことも。
ご本人には悪気がなくとも、次のゲストにとっては「焼け跡のあるベンチ」に座るのはやや気が引けるもの。
運営者にとっては修繕や交換の対応に追われる原因になります。
自然に伝える、スマートな“注意喚起”のあり方
ゲストの自由やくつろぎを大切にする貸別荘にとって、「何々は禁止」と強く言いすぎると、雰囲気が固くなってしまう。
だからこそ、伝え方には少しだけ工夫が必要です。
たとえばこんな表現があります:
📌 室内は煙感知式の火災警報器が作動しやすいため、
お線香や蚊取り線香など、煙の出る製品のご使用はご遠慮いただくようお願いしております。
📌 ウッドデッキや屋外家具の上での熱を伴う製品のご使用は、
焦げ跡など設備の劣化につながることがあるため、ご注意ください。
📌 お持ち込みの虫除けグッズのご使用についてご不明な点があれば、
事前にご相談いただければ安心です。
いずれも「禁止」とは書いていません。
でもゲストにとっては、「あ、これは使わない方が良さそうだな」と自然に伝わります。
トラブルが起きてからでは遅い。だからこそ“予防”の姿勢を
運営者側としては、「誰も蚊取り線香を使うなんて思っていなかった」と後から対応に追われるのではなく、“使うかもしれない”という前提で備えることが大切です。
-
ハウスルールやマニュアルでの表現をやわらかく統一する
-
チェックイン前の案内メッセージにさりげなく盛り込む
-
室内に1枚「煙に関する注意書き」を掲示する(多言語対応がベスト)
-
デッキや庭先にも「熱や煙に弱い素材が使われています」などの補足を掲示
これだけでも、ぐっとトラブルの発生率は下がります。
“安全を守ること”は、“くつろぎを守ること”でもある
宿泊施設を訪れるゲストは、心を緩めに来ています。
だからこそ、「火災報知器が鳴る」「警察や消防が来る」「焦げ跡を見つけてヒヤッとする」——そんな思いをさせないことが、くつろぎを守る最大の方法なのです。
一つひとつの細やかな配慮が、結果として施設の評価やリピート率にもつながります。
まとめ:蚊取り線香は悪者ではない。でも“場所”と“伝え方”がすべてを決める
蚊取り線香そのものが危険なのではありません。
問題は、「どこで・どう使われるか」を適切に伝えられていないことです。
「煙が出るものには気をつけてほしい」
「デッキなどには高温のものを置かないでほしい」
そうした想いを、やわらかく・でも確実に伝える仕組みがあることで、
ゲストの満足も、施設の安全も、どちらも守ることができます。