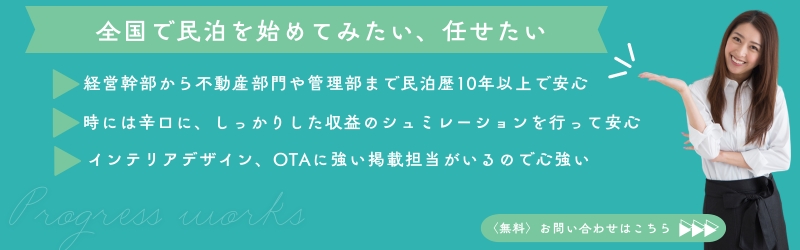民泊投資のメリット・デメリット:賃貸型と売買型を比較して見える現実

観光需要の高まりやインバウンド回復の追い風を受け、「民泊」は今なお注目される不動産投資のひとつです。しかし、民泊と一口に言っても、その投資スタイルは大きく分けて「賃貸による運用」と「売買(購入)による所有・運用」の2種類があり、それぞれに明確なメリットとリスクが存在します。
ここでは実際に数多くの民泊施設を運営してきた立場から、「賃貸型」と「売買型」それぞれの特徴について、実例を交えながらご紹介します。
賃貸型の民泊投資:小さく始めて、利益を逃さない
▼メリット
① 一括損金で経費計上が可能
賃貸型は初期投資の大部分が「内装費」「備品購入費」「広告宣伝費」などで構成されます。これらは基本的に一括で経費計上が可能なため、初年度の所得に対して大きな節税効果が期待できます。
② 所得税の還付が狙える
事業として万が一、赤字になった場合でも、他の所得と損益通算が可能であれば、所得税の還付を受けることができます。特に給与所得と合わせた節税スキームとして注目されています。
③ 投資額に対して高利回りが実現
運用がうまくいけば、投資額に対しておおよそ20%前後の実質利回りを実現することも可能です。賃貸物件ゆえにイニシャルコストを抑えられ、短期回収に優れたモデルと言えるでしょう。
▼デメリット
① 建物資産が残らない
当然ながら建物を所有していないため、売却益や資産形成の側面では不利です。
② 契約更新・退去リスク
物件オーナーとの契約が更新できない、途中解約されるリスクがあり、長期視点ではやや不安定な面があります。ですが弊社ではそのようなリスクを最大限に排除した賃貸借契約をしております。
③ 民泊として賃貸が可能な物件がなかなか出てこない
民泊として賃貸可能な物件は数が少なく、条件に合う物件がなかなか市場に出てきません。さらに需要が高いため、家賃相場も割高になりがちで、収益性が圧迫されるケースもあります。
売買型の民泊投資:資産形成+節税のハイブリッドモデル
▼メリット
① 高い利回りが狙える
民泊運用前提の物件は、通常の居住用賃貸に比べて**表面利回り15%以上(実利7.5%程度)**が狙えるとされています。特に観光地では需要が集中するため、閑散期と繁忙期をうまく乗り切るノウハウがあれば、非常に安定した収益源となります。
② 建物の減価償却による節税
建物を所有することで、法定耐用年数に応じて減価償却が可能です。特に木造や軽量鉄骨の中古建物は、償却期間が短いため節税効果が高く、初年度に多額の経費計上ができる点も魅力です。
③ 一般住宅で賃貸できない物件に活路
駅から遠い、間取りが特殊、築年数が古い――こうした物件でも民泊需要があるエリアであれば「眠れる資産」が収益物件へと変わる可能性があります。再販時の戦略次第では、出口戦略としても有効です。
▼デメリット
① 初期投資が大きい
当然ながら購入型は土地・建物代に加え、登記費用、固定資産税、仲介手数料などがかかるため、スタート時点での資金ハードルは高くなります。
② 地域制限・法令変更リスク
民泊新法や条例変更によって営業が制限されるケースもあり、特に住宅専用地域では用途制限を受ける可能性も。将来の法改正や行政対応への備えは欠かせません。
③ 長期目線でのリスク管理が必要
突発的な修繕費や税制変更、観光需要の変化に柔軟に対応できる戦略が必要です。また、運用が難しい場合は「売却できる物件かどうか」の目利き力が問われます。
まとめ:どちらが正解ではなく、「どちらが自分に合うか」
民泊投資は、「小さく始めて早期回収したい人」には賃貸型、「資産を残しながら節税もしたい人」には売買型が向いています。それぞれにリスクとリターンがあり、一概にどちらが優れているとは言えません。
重要なのは、「投資としての目的(短期回収/節税/資産形成)」と、「自分の資金計画・運用体制」に照らして適切なスタイルを選ぶことです。
現在では、特区民泊や旅館業取得済みの物件など、行政認可履歴のある収益型物件も増えており、安心して投資に踏み出せる環境も整いつつあります。
もしあなたが民泊投資に興味をお持ちなら、まずはご自身のゴールを明確にし、「小さく試してから大きく育てる」スタイルをお勧めします。