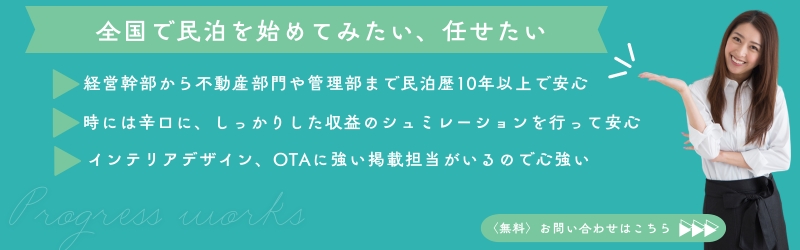特区民泊“新規停止”が濃厚に──小規模運営代行会社、今静かに撤退の足音
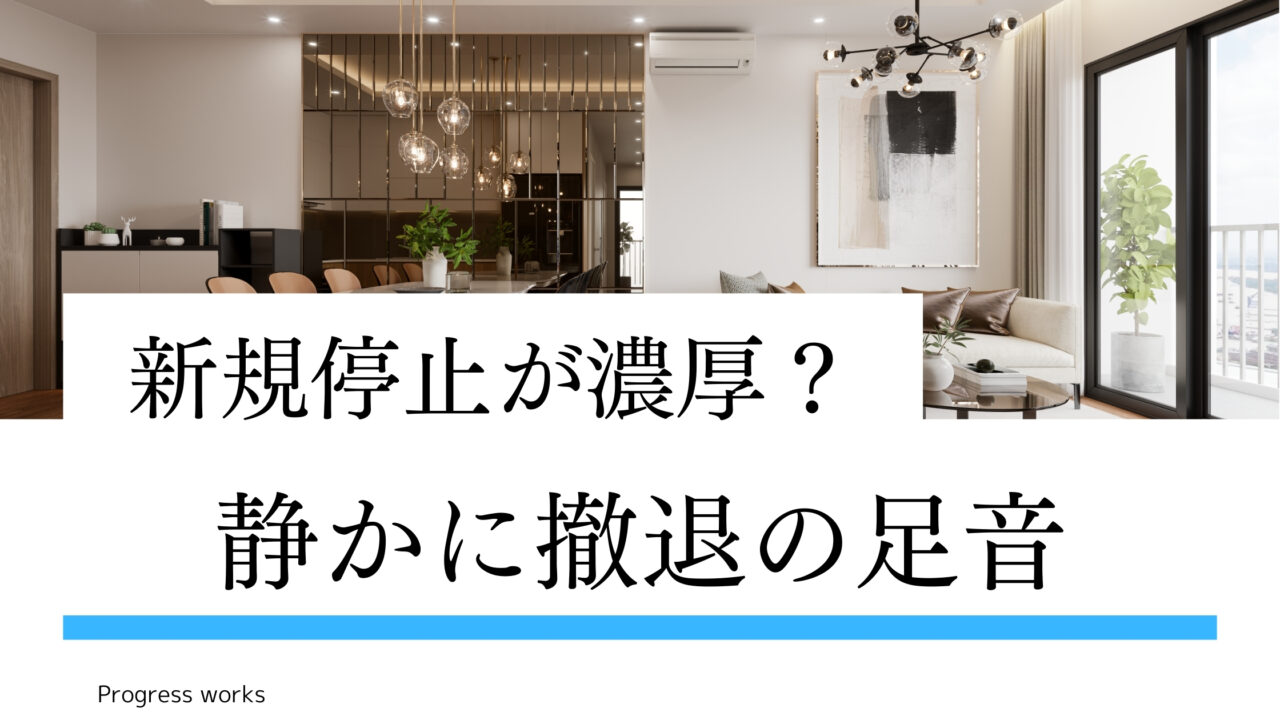
2025年夏、大阪を中心に広がっていた特区民泊の運営環境が、大きな転換点を迎えようとしています。
行政トップによる「新規認定の受付停止」発言から数ヶ月。実際に大阪府と市は制度見直しへと舵を切り、各市町村にも“制度継続の是非”を問う動きが本格化。こうした中、水面下では小規模の民泊運営代行会社が、すでに撤退準備を始めている可能性が高まっています。
表向きには「引き続き運営中」「新規案件ご相談ください」と言っている代行業者も、内心では「これは潮時」と判断している、そんな静かな空気が流れ始めています。
新規施設の工事が“現場レベル”で止まり始めている
さらに、目に見える形で「終わり」が始まっているのが現場工事のストップです。
特に西成区などでは、新たな特区民泊施設の着工が一時停止になっていたり、施工業者が“凍結”を指示されるケースが出てきています。
現場監督や工務店からも、
「行政判断がハッキリしないから、とりあえず工事中断です」
「あとで制度が変わって営業できなくなったら無駄になる」
といった声が出ており、“制度が確定するまで様子見”という空気が、現場の最前線にも広がっているのです。
これは、「制度の終焉」が政治の話や法律の話ではなく、現場でリアルに起きている、ということを意味しています。
予兆はすでに始まっている:止まった新規相談窓口
2023〜2024年頃まで、特区民泊の新規運営相談は、毎月のようにウェブ広告やSNSで打たれていました。「あなたの物件を収益化!」「365日営業可能、投資回収最速!」といったうたい文句が踊る広告は、目新しい投資先を探す個人投資家たちを多く呼び込みました。
しかし、2025年に入ってから、そうした広告が激減。代行業者の公式サイトの「新規問い合わせフォーム」がひっそり閉じられているケースや、「お問い合わせは現在停止中」といった注記が増えています。
新規獲得に前のめりだった代行会社が、あからさまに守りに入っている。
これは、“そろそろ逃げ出す準備”に入ったサインと言えるかもしれません。
特区民泊の終わりが意味すること:小規模事業者への打撃
特区民泊は、住宅宿泊事業法の180日制限を受けず、年間365日営業が可能という大きなメリットがありました。そのため、運営代行会社にとっては高稼働率が前提のビジネスモデルが成立していたのです。
しかし、制度が見直されると…
-
新規物件の受付停止(=ビジネスの入口が閉じる)
-
一部区域での運営停止・認定取り消し(=既存顧客の物件も将来的に稼働困難に)
-
住民クレームや条例対応による追加コスト(=収益性の悪化)
こうしたリスクが現実になり始めます。体力のない小規模事業者にとっては、**「新規開拓ができない」=「いずれジリ貧」**という意味です。
すでに手数料収入で回している小規模代行業者の中には、すでにこうした展望を読み、「今のうちに撤退を決めた方が傷が浅い」と判断している会社もあるでしょう。
小規模代行業者からのSOS:「うちではもう持ちきれない」
私たちが民泊・宿泊施設の運営支援を行う中で、2025年夏頃から明らかに増えているのが、**他の小規模運営会社からの“委託相談”**です。
-
「運営を続けるのがしんどくなってきた」
-
「今のスタッフ数ではトラブル対応が追いつかない」
-
「制度変更に対応できる体制がない」
-
「新規が取れないと先が見えない」
こうした声とともに、「既存施設の管理を引き継いでもらえないか」「撤退のサポートだけでも頼めないか」という相談が、実際に寄せられています。
代行会社の撤退は、決して“他人事”ではなくなってきています。とくに、特区民泊に特化してビジネスを組み立ててきた小規模事業者にとって、“新規認定のストップ”は生命線の切断に他なりません。
「撤退」は音を立てずに進む
この業界の特徴として、撤退や縮小は大々的にアナウンスされないことが多いです。
理由は簡単で、代行業者には「現在の顧客(=物件オーナー)」が存在しており、彼らとの契約は続いているから。
ここで「撤退します」と宣言してしまえば、残ったオーナーも一斉に離れてしまう可能性があります。
そのため、撤退は徐々に進行します。
-
新規募集をやめる
-
スタッフを自然減で整理
-
現場清掃や点検の頻度を徐々に縮小
-
問い合わせのレスポンスが遅くなる
こうして“フェードアウト型の撤退”が静かに進み、気づいた時には「連絡がつかない」「運営が止まっている」という状態になりかねません。
オーナー側にも影響が出始めている
特区民泊に特化して代行業者を選んだ物件オーナーたちにも、今後は厳しい局面がやってきます。
「この会社に任せておけば安心」という信頼が、ある日突然ぐらつく。
実際、2025年夏以降、特区民泊のルール変更に関して明確な説明がされていない、サポートが急に雑になったという声も出始めています。
一部のオーナーは、代行業者から「別エリアへの物件移転」や「用途変更」を促されているという話もあります。これは、運営側がすでに制度の限界を認識し、“着地戦略”を始めていることを意味しています。
小規模代行業者の今後:二極化の時代へ
この流れは、「撤退する小規模代行業者」と「体制を整えて生き残る中堅以上の会社」との間で、明確な二極化をもたらすことになります。
今後は以下のような動きが想定されます:
-
撤退組:サイレントクローズ、他事業への転換、事実上の自然消滅
-
生き残り組:住宅宿泊事業法物件・簡易宿所・旅館業などへの移行提案、管理対象の再構築、法制度への柔軟対応
オーナーにとって重要なのは、どちらの代行業者と組んでいるのかを見極めることです。
特に、「問い合わせへの対応スピードが急に鈍くなった」「将来の方針について何も説明がない」という場合は、警戒信号です。
終わりではなく、再構築のタイミング
今回の特区民泊の“新規受付停止”は、確かに一つの終わりを示しています。
でも同時に、制度の見直しによって、より健全で長期的な宿泊ビジネスが生まれるチャンスでもあります。
今後は、旅館業・簡易宿所への転換、商業地への移転、中長期滞在向けへのリブランディングといった「次の一手」を持つオーナーや運営会社が生き残っていきます。
そのためにも、現状にしがみつくのではなく、今の運営体制が「未来にも対応できる体制か」を改めて見つめ直すタイミングです。
最後に:変化に背を向けるのではなく、動く準備を
特区民泊は一時期、大阪の宿泊ビジネスを大きく変えました。
しかしその構造は、“制度のゆるさ”の上に築かれた砂上の楼閣でもありました。
私たちの元には、今まさにその砂が崩れ落ち始めたことを示す相談や委託依頼が、リアルに届いています。
そして現場では、新しい建物が完成することなく止まり、職人たちは次の現場に移っています。
今、必要なのは、「終わる」という事実を受け入れ、「どう次に向かうか」を考える力です。
物件オーナーにとっても、運営会社にとっても、
それがこの市場で“生き残るための唯一の道”になるでしょう。